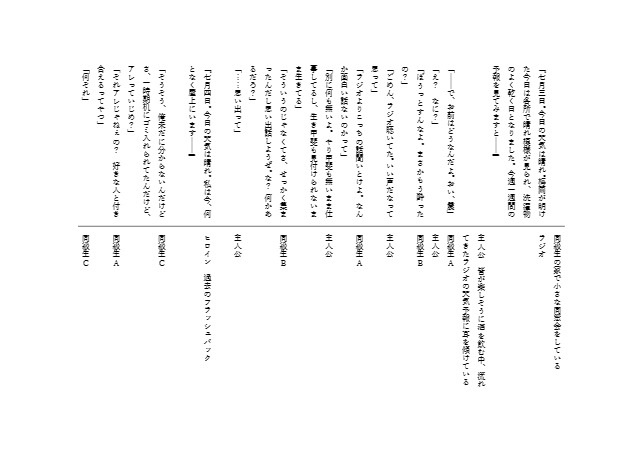一度映画企画として挙がった脚本を小説に起こしてみました。
添付されてるシナリオと合わせてご一読ください。
予定主題歌 ヨルシカ / 声
カチカチ。
ラジオのダイヤルを回す音。そして、周波数を合わせる音。
『七月三日。今日の天気は晴れ。梅雨が明けた今日は各所で晴れ模様が見られ、洗濯物のよく乾く日となりました。今週一週間の予報を見てみますと──』
窓の外を見る。時刻は午後十時半を少し回ったところ。言われてみると確かに、夜空は深く澄んでいる。青空の色を忘れてしまいそうなほどの星が瞬いている。視界のピントをずらすと、同窓会という名目で缶ビールを呷る友人達の姿がはっきりと映っている。
人の声が好きだった。一時的にでもこの心の穴を埋められるなら、誰の声でもよかった。
人が最初に忘れるものは、人の声だという。だからというわけでもないけど、誰かの声を覚えておきたいと思うようになった。でも。
「──で、お前はどうなんだよ。おい、震」
「え? なに?」
友人に肩を揺さぶられて意識が戻る。その拍子に握っていた缶ビールから中身が少し零れる。
「ぼうっとすんなよ。まさかもう酔ったの?」
「ごめん、ラジオ聴いてた。いい声だなって思って」
「ラジオよりこっちの話聞いとけよ。なんか面白い話ないのかって」
缶ビールに口を付ける。別に冷たくもない発泡酒の苦みが口に広がる。はっきり言って美味しくはない。
「別に何も無いよ。やり甲斐も無いまま仕事してるし、生き甲斐も見付けられないまま生きてる」
いつからだっただろうか。忘れてはいけないものを、忘れていくようになったのは。何も無い一日とか、あの日の青空とか、何かの大それた意味とか理由とか。そういうものを手放した瞬間が僕にもあったらしい。それすらももう忘れてしまった話だけど。
「なんかお前、卑屈になってね?」
「震はずっとこういう奴だったぞ」
「そういうのじゃなくてさ、せっかく集まったんだし思い出話しようぜ。な? 何かあるだろ?」
「……思い出って」
人が最初に忘れるものは、人の声だという。だからというわけでもないけど、誰かの声を覚えておきたいと思うようになった。でも。
『七月四日。今日の天気は晴れ。私は今、何となく屋上にいます──』
あの瞬間の、あの彼女の声だけは、今も僕を離してくれないままだ。
「そうそう、俺未だに分からないんだけどさ、一時期机にゴミ入れられてたんだけど、アレっていじめ?」
友人の一人が思い出したように話す。僕は手持ちの缶が空になり、新しい缶ビールのプルタブを起こした。
「それアレじゃねぇの? 好きな人と付き合えるってやつ」
「何それ」
「好きな人の机に自分の名前を書いた紙入れて、しばらく見つからなかったら両想いになる、みたいなの。あったよな?」
「は? 俺ろくに見ずに捨ててたんだけど」
「うわ、もったいねえ。付き合えてたかもしれないのに」
「それ高三の時の話だろ? 運が良ければ結婚だってしてたかも」
「うわぁー! 早く結婚してえー!」
僕がいなくても楽しくやってただろうなと思いながら、テーブルの上のお菓子に手を伸ばす。自分はここにいなくてもいいなという疎外感とか、自分がここにいるからこそ生まれる罪悪感とか。人生はそういうものの繰り返しらしい。ラジオの音量を上げる。
『さて、続いては大人気コーナー、恋のお悩み相談室です! 今回もたくさんのお便りをありがとうございました! お便りを読ませて頂いて、私も高校生に戻りたくなっちゃいました! あ~、タイムスリップとかできたらな~』
「まあでも」
笑いが少し治まり、余白に挟み込むように友人がぽつりと呟く。
「学生時代の恋愛ってこういうもんだよ。どうせこの先の人生もずっと後悔し続けるんだろうな。この後悔が消えたらいいのに、って思いながら」
その瞬間、僕は開けたばかりの缶ビールを一気に流し込んだ。冷えてもいない、美味しくもないビール。友人が「こいつマジか」とはやし立てる。
「おい、震がやる気だぞ」
「いけいけ! 全部飲め!」
「一気! 一気!」
後悔はきっと、全てを過去形にした人間の特権なのだと思う。だから、何も終わらせられない僕のこの感情は、きっと後悔ではない。じゃあ一体、この感情はなんなのか。未だに分からない。彼女を思い浮かべる度、彼女の声を思い出す度、僕はただひたすらに、どうしようもなく。
『震』
どうしようもなく、泣きたくなる。
* * * * *
『俺も楽しかった。また集まろうぜ。二日酔いお大事に』
友人からのメッセージにスタンプを送信し、携帯をポケットにしまう。無理な飲み方をしたせいか少し気分が悪い。
体調の悪い日に浴びる直射日光ほど憎らしいものは無いと思う。空を見上げてみると、文字通りに一点の曇りも無い青空が遠く澄んでいる。こういう時、夏が嫌いになる。高校時代の僕は夏が好きだったはずなのに。いや、「彼女」と共に過ごした夏だったからこそ、そう思えてしまうのだろうか。
昨日の同窓会で変な話をしてしまったせいか、そういうどうでもいい事を考えてしまう。いい加減終わらせないといけないのに。いい加減過去形にしなければならないのに。二日酔いで回らない頭が、そういう自責の念だけはくっきりと浮かび上がらせる。
家に帰って冷たい水を飲もう。もう少しだけ睡眠を取ろう。そうやって雑念を振り払おうとした時。ふと、自分の歩いているこの場所が高校時代の登下校の道である事に気が付いた。
友人の家から僕の家までは、この道を歩かなければならない。もうこんな道、歩く事はないと思っていたのに。回らない頭が今度は痛みを連れてくる。
しばらく歩き、高校の前にまで辿り着く。何事もなく通り過ぎようとしたのに、視界の隅に校舎を捉えた瞬間、僕は思わず立ち止まっていた。
『この後悔が消えたらいいのに、って思いながら』
昨晩の友人の言葉がフラッシュバックする。その時、僕は妙な事を思い付いた。ポケットにしまったばかりの携帯を取り出し、友人に再度メッセージを送る。
『あのさ、昨日高校時代の話したじゃん。卒業生って中に入れたりしないかな』
『高校って、俺の家の近くの?』
返信はすぐに来た。『それそれ』と肯定する。
『覚えてないのかよ。老朽化とかで高校の住所は移動しただろ。その校舎自体はもう使われてないぞ』
確かに、校舎をよく見ると年季が入っているというか、どうにも人の立ち入りが感じられない。窓ガラスや壁はひび割れ、雑草があちこちで茂っている。
つまり、今は誰も人がいないわけだと、痛む頭でそんな事を考えた。
『犯罪者になってもいいなら入れるかも、なんてな。 ……入らないよな?』
友人のメッセージを確認し、スマホに有線イヤホンを挿す。ラジオを聴けるアプリを立ち上げ、またポケットにしまった。
『七月四日、今日の天気は晴れ。観測図から梅雨前線が消え、日本全土での夏入りとなりました。日焼け対策をし、熱中症には充分お気を付けください。また、明日からは急激に気温が──』
周囲を少し確認し、素早く校門を飛び越える。
敷地に足を着地させた瞬間、数年前の幻影を鮮明に見てしまった。あの日々の続きをなぞるかのように。ともすれば、僕は学ランを着ているのではないかと錯覚してしまうほどに。
全部覚えている。ここは少し段差があって転びやすくなってるとか、ここは窪んでいて雨の日には水溜まりができるとか、あそこには名前も知らない花が一本だけ咲いているとか。三年間で目に焼き付けた光景が、そこにある。昨日の飲み会で話した事を思い出すよりも先に思い出せる。
僕が今やっている事は、もちろん立派な犯罪だ。どうしてこんな事をしているのか、僕にも分からない。昨日の会話が原因かもしれないし、二日酔いで頭が回らないという言い訳かもしれない。でも、そんなのは全部詭弁だと分かっている。どこまで行ったって、僕の欲しいものは、求めているものはたった一つだ。世界でたった一つだけの、あの空気の振動だ。
『ねえ、震』
校舎の扉には鍵がかかっておらず、すんなりと開ける事ができた。こうなるともう自制は効かないと自分で分かっていた。誰の気配も無い、埃っぽい校舎に足を踏み入れる。まずは昇降口からすぐの階段を上る。一階、二階、三階。三階に着いて、突き当りの廊下を真っ直ぐ進む。
機械、というのも違う。僕の中の本能みたいなものが足を動かしていた。つまり、僕が向かっているのは僕が通っていたクラスだ。
長い廊下の先、もうすぐで目的地というところまで来た時だった。
「……は、……にこ、……な」
イヤホンの外から、人の声のような音が聞こえた気がした。まさか、そんなはずはない。いや、ここを管理している関係者かもしれない。見つかったらどうやって言い訳しようか。そんな事を考えながら歩き、教室の前に辿り着く。そして、イヤホンを外した瞬間。
「三月九日、今日の天気は晴れ。卒業式の後で教室にいたら、いつの間にか学校から人が消えていました。さすがの私でも違和感を覚えてます。しかもなんか蒸し暑いし。意味が分かりません。とりあえず家に帰って──」
教室の中から、声がしたのだ。
間違いじゃなければ、……いや、間違いじゃない。その声は、僕がこの数年で嫌と言うほど反芻した声だ。この世界で、この世で、たった一つだけの空気の振動だ。数年ぶりに、鼓膜が同じ揺れ方をしているのだ。
痛いほどに鳴る鼓動を無視し、教室の扉を開ける。
教室の中心にいたのは、制服を着た一人の女子生徒だった。
「……朱音」
「……震?」
カチカチ。
彼女がレコーダーのダイヤルを回す音。
そして多分、僕らの周波数が重なる音。
* * * * *
生まれて初めて地下から飛び出した人間が、本から得た知識だけで描いたような「夏」の青空の日。校舎には熱気が充満していて、僕はたまらず立ち入り禁止の屋上へ避難しようとしていた。
「七月四日。今日の天気は晴れ。私は今、 何となく屋上にいます──」
扉を開けようとした時、向こう側から声がしたのだ。この高校に入学してから二年間、屋上は僕一人が使ってきたお気に入りの場所だった。
思わず溜め息を吐く。聞くに女子生徒の声らしかった。もうここは使えないかもしれない。また新しく一人になれる場所を探しておこう。そう思いながら、せっかくだからと扉を開ける。
屋上は綺麗な正方形の形をしていて、それを少し背の高い柵が囲んである。そのど真ん中に、一人の女子生徒が座り込んでいた。僕に背を向ける形だ。
「とにかく暑い。屋上なら少しはマシかなと思って来てみたのにちっとも涼しくありません。なんなら校舎より暑い気がする──」
そこまで言った時、人の気配に気が付いたらしい。女子生徒は体育座りの態勢のままこちらを振り向いた。
容姿には取り立てて特徴の無い女子だった。どこにでもいるような、あるいはどこかで見た事があるような、そんな感じだ。強いて言うなら、少し切れ長の目が睨みつけるような鋭い視線を送っているくらいだろうか。
「……なに?」
僕を睨みながら、彼女が言った。
それが、初めて聞いた彼女の声だった。
その声は、まるで僕の人生のアナウンス担当かのように僕の中に馴染んだ。神様が言葉を発するとすれば、きっとこんな声なのではないかと思った。
「いや、何してるのかなって思って」
「何って、見れば分かるでしょ。録音」
「それは分かるけどさ」
彼女は右手に細長い機械のようなものを握っていた。ボイスレコーダーか何からしい。それをポケットにしまいながら、「君こそ」と僕に言葉をかける。
「屋上まで何しに来たの? ここ立ち入り禁止だよ?」
「ここなら風が吹いて少しは涼しいかなって思って」
「残念だけど期待外れ。全然」
「そうみたいだね。聞こえてたよ」
僕が言うと、彼女は「うわ」と言って露骨に顔を顰める。
「聴いてたの? 趣味悪いよ」
「聴いてたんじゃなくて聞こえてたんだって」
「同じじゃん」
彼女が苦笑いするように呟く。「聴く」と「聞く」の間にはそれなりの距離があると思うのは僕だけだろうか。
後ろに手をつき、彼女は青空を見上げた。何も無い青空だ。世界全部が青色で満たされればいいのにと祈ってしまうような空だ。こんなにも近くて、こんなにも遠い。
「君、名前は?」
「……震。なんで?」
「盗聴犯の名前くらいは覚えておこうと思うって。あ、私は朱音。忘れないでね」
彼女は僕を見てほんの少しだけ口角を上げた。今度は僕が顔を顰める番だった。
「何を録音してたの?」
ふと気になって訊ねる。彼女はボイスレコーダーの入ったポケットをさすりながら「別に」とぶっきらぼうに言った。
「その日あった事とか。何も無い日だったら『何も無い一日でした』で終わりだし」
「何の為に?」
「意味なんか無い。日記と同じだよ」
「じゃあ日記でいいじゃん」
「ごちゃごちゃうるさいなあ」
僕の言葉を遮るように言った彼女は、突然立ち上がるとおもむろに僕との距離を詰めた。
「あのね、世の中の全てに理由とか意味があると思ったら大間違いだよ。人間が生まれてくるのに理由も意味も無いのと一緒。私が自分の声を録音してる事に何かを見出そうとするだけ無駄。これだけは忘れないで。分かった?」
彼女はそう言って僕の顔を指差す。
全てに理由や意味があるわけではない。理由や意味も無く、見つけられずにのうのうと生きているのだからそうだろう。彼女の言葉には妙な説得力があるような気がした。いや、それすらも彼女の声がそうさせるのだろうか。
僕がゆっくり頷くと、彼女は「よし」と初めてちゃんと笑った。切れ長の目が細くなり、印象が変わるくらい可愛らしい笑顔だった。
「じゃあ私は戻るから。君も早く戻りなよ」
そう言って手を振り、屋上から出て行こうとする。僕は力なく「あ、うん」と呟く。
「あ、そうそう」
扉に手をかけた彼女が、何かを思い出して振り向いた。僕を指差し、口を開く。
「『何も無い一日でした』って録音するのにはもう飽きてるの。何か面白い事があったら教えてね。これも忘れないで」
それだけ言い残し、もう一度手を振って今度こそ屋上から出て行く。
屋上には何も無い。ただ耳が痛いくらいの静寂だけが取り残されていた。
* * * * *
初めて彼女を見た時と同様、切れ長の鋭い目が僕を睨んでいる。彼女が本当に朱音であるか疑問だったし、目の前の彼女も僕が本当に僕なのか自分を疑っている。お互いにそうだっただろう。
「……君、誰?」
とりあえず、僕の方から声をかけてみる。彼女は「こっちのセリフ、です」と、とりあえずといった感じで敬語交じりに言った。
「そっちこそ誰? 震? なんか老けた?」
向こうは僕の名前を知っている。彼女が朱音である事は間違いないらしい。でも、数年前の姿をした朱音がここにいる事はもちろんおかしい。あの時間で脳に焼き付けた彼女についての記憶と、あの日々の朱音がここにいるという非現実。僕はどちらを疑うべきなのだろう。
その時、僕の脳裏に誰かの声がよぎった。どうしてこのタイミングだったのか分からない。それでも、つい最近聞いたような気がする誰かの声が鳴ったのだ。
『あ~、タイムスリップとかできたらな~』
まさか。そんな事があるだろうか。いやでも、回らない僕の頭ではそれ以外には思い付かない。
目の前にいる非現実を見つめる。「なに、ですか」と警戒したままの朱音に、僕は言葉をかけた。
「僕らが出会った日にちと場所、言える? あと、どんな出会い方だったか」
「何で」
「いいから」
少しだけ強い口調で促す。朱音は眉をひそめ、思い出すように「えっと」と答えを口にした。
「七月四日、屋上。盗み聞きがどうとかって話した。いや、貴方が震だと仮定した上でだけど」
大きく息を吐く。間違いない。目の前にいるのは朱音だ。だけど、数年ぶりの再会というわけではない。どういう事か、あの日々のままの、高校三年生の朱音。つまりはやはり、タイムスリップをしたという事。
「一応本当みたいだね。納得するしかなさそうだ」
僕が言うと、朱音は「いやいや」と少し焦った様子で言った。
「ちょっと待ってよ、私はしてないんだけど。本当に震なの?」
「まあ」
「まあって何よまあって。なんか証明してよ」
今度は苛立ったように言う。確かに彼女の言う事も一理ある。どういうわけか、目の前には成長して少し老けたクラスメイトがいるのだ。そういう反応にもなるだろう。けれど。
「証明って……」
急に言われても、そんなもの用意しているはずがない。一応財布はある。免許証を見せるか? いや、そういう話でもないだろう。理論ではなく、本能で納得しなければ気が済まないのだ。つまり、僕が僕であると、心で理解したいのだ。
「……君の名前は、朱音だ」
僕が言うと、朱音は眉をひそめて「なに今更」と訝しんだ。僕はそれに「まさか、忘れたの?」と続ける。
「君が言ったんだろ。朱音って名前を、 忘れるなって」
そう言うと彼女は少し驚いたように目を見開いた。どうやら納得したらしい。「まあいいや」と息を吐く。
「じゃあ本当に震だとして、老けてる理由は? あと急に暑くなった理由。まさかタイム」
「タイムスリップだろうね。理由は知らないけど」
また彼女の言葉を遮るようにして断言する。朱音は「本気?」と少し馬鹿にするような言い方をした。僕が老けているのは認めるけど、タイムスリップしたとは信じられないらしい。
とりあえずと思い、ポケットからスマホを取り出してそこに表示されている日付を見せる。しかし朱音は「なにこれ」とスマホを人差し指と親指で摘まんだ。そうか、まだスマホも珍しい時代だったか。
僕はスマホを操作し、さっきまで聴いていたラジオのアプリを開く。そして有線のイヤホンを外して、スピーカーでボリュームを大きくした。
『……やっぱり十年前と言えばあれですね。ノストラダムス、じゃなくて、えっと、忘れちゃいました。でもほら、地球滅亡説があったじゃないですか。〝2012 〟なんてSF映画もあったくらいですよ。私もどうせ地球が終わるなら宿題とかしなくていいやって思ってたらめちゃくちゃ学校始まるっていうね』
「……マジ?」
朱音が信じられないものを見る目と声で訊ねる。僕が小さく頷くと、近くにあった席に座って頭を抱えた。僕も同じ気持ちだ。
それからしばらくは、お互いに何か言うでもなく無言の時間が続いた。でも、このままで事態が進展するわけでもない。僕は一つ咳ばらいをし、彼女に短く訊ねる。
「えっと、どうする?」
「どうするって、私に訊かれても」
「……ごめん、言い方を間違えた。君はどうしたい? 十年前に戻りたい?」
彼女はずっと難しい顔をしていたが、僕が訊ねると「まあ」と小さく深呼吸をした。
「ここにいてもしょうがないし、戻らないといけないよね」
「じゃあ戻る方法を考えよう」
「どうやって?」
「それが分からないから考えようって言ってるんだよ」
現状を整理する必要がある。今の僕と今この場所は、僕の時代だ。となれば、イレギュラーなのは朱音だけ。彼女さえ元の時代に戻ればいい。彼女が戻るべき時間を把握しておいて損はないだろう。
「とりあえず、ここに来るまでの事を教えてよ。卒業式の後だっけ?」
僕が訊ねると、朱音は小さく頷き、僕に思い出させるようにあの日の事を語った。
「もしかして覚えてない? 卒業式の後、 私達──」
* * * * *
「三月九日、今日の天気は晴れ。言わずもがな卒業式の日です。ずっと立ちっぱなしで足腰が痛い。疲れた。震もしんどそうにしてます」
「してない」
「ちょっと邪魔しないでよ。……えっと、なんだっけ」
朱音は頭をガシガシと掻いて、「忘れた。もういいや」と投げやりにボイスレコーダーをポケットにしまった。
「最後の日なのにそんな適当でいいの?」
「疲れたって言ったでしょ。もう録音する気力も無いの」
「もったいない」
なんとなく口を出た「もったいない」。それはもちろん、今日が高校生活最後という意味を含んでいる。けど、それがなんだとも同時に思う。一分一秒が最後で、今この瞬間が最期なのはいつだってそうで。でも、それを分かっていても時間をゴミみたいにしか扱えない。それがまるで人間の証明だとでも言うように。「もったいない」なんてのは、人間から外れるほど時間を効率よく消費する奴の使う言葉かもしれない。
高校生活を終えて何者でもなくなった僕らは、それでも静かな教室で時間を無駄遣いしていた。間違いなく、悲しいくらいに人間だった。
「……もうこれで終わりなんだね」
朱音が誰に言うでもなく、独り言のように言う。僕は返事をするか迷って、小さく「そうだね」となんとなく同意した。それと同時に、どうでもいい野暮な疑問も浮かんだ。
「楽しかった?」
「何が」
朱音に逆に訊ねられ、別に大した事を考えていなかった僕は「いや、なんとなく」と呟く。
「学校生活っていうか、人生って言うか。ほら、何も無い一日には飽きたって、 君が言ってただろ」
「……よくそんな事覚えてるね」
「忘れるなって言ったのは君だ」
「そうだっけ」
朱音が少し笑いながら言う。そして少し考えるような間を置いた後で、「そうだね」と自分に、あるいは誰かに言い聞かせるように言った。
「空は飛べなかったし、世界は終わらなかった。けどまあ、それなりに楽しかったよ」
劇的な何かがあったわけじゃない。ただ時間は過ぎ去った。でも、たったそれだけの事が僕らにとっては全てだった。彼女と出会ったあの瞬間、僕の世界は間違いなく変わった。彼女と過ごした日々が、僕にとっての世界だった。そういうものを一々言葉にしたかった。でも、どこをどれだけ探したって、それに相応しい言葉は無いのだろう。
「……僕も程々に楽しかったよ」
だから結局、こんな風な言い方しかできない。それが少し悔しくもあって、少し嬉しくもある。これだけの言葉に、精一杯の僕の感情を詰め込む。
朱音にそれが伝わったかどうか分からない。彼女はいつもの調子で「ふーん」というだけだった。それでよかった。伝わらなくてもいい。言葉という入れ物に、僕の世界全部を詰め込んで君にあげよう。それが、僕に最後にできるせめてもの信仰だ。
「……じゃあ、僕はそろそろ帰ろうかな」
しばらく続いた沈黙に耐えられず、先に音を上げる。今まではこんな事なかったのに。
僕が立ち上がると、朱音は座ったまま「うん」と小さく零した。
「君はどうする?」
「私はもう少しここにいるよ。少し眠って帰ろうかな」
「そっか」
少し迷った。このまま帰っていいのだろうか。多分、彼女と会う事はもうないだろう。せめて何か言葉をかけた方がいいと少し思う。でも、無駄な言葉を重ねてしまうくらいなら、静かに別れるべきだとも思う。
「ねえ」
そんな葛藤をしていたら、彼女が先に口を開いた。僕は「え?」と少し間抜けな声を出す。
「えっと、これも忘れないで欲しいんだけどさ。その、私」
そう言って彼女は座ったまま、自分の指先だけを見つめていた。
発した言葉が違和感になるのに充分な沈黙が訪れた後、意を決したように一度僕の顔を見つめ、結局は「いや」と迷いながら首を横に振る。
「何でもない」
「なんだよ」
「何でもないってば。眠たくて忘れちゃった」
今の様子を見ていれば、何でもない事くらい僕にでも分かる。何か言いたかったのだろう。でも、彼女は口を閉ざす事を選んだ。なら、そうするべきなのだろう。僕は「そう」と気持ちを呑み込む。
「えっと、じゃあ」
「……うん。じゃあね、震」
「さよなら。朱音」
それで、僕は教室を出た。多分、かけるべき言葉はもっとあっただろう。やるべき事はもっとあるだろう。それでも、いつだってこうやって生きていくのだ。それが人間だから。今に限った話じゃない。
廊下を進み、ふと窓の外を見る。空は夏のように晴れている。
そこから見える屋上を眺め、世界が変わったあの瞬間を思い出した。彼女と出会った日を。彼女の目はいつも、秋のように涼し気だった。
強い風が吹いて、桜の花弁がそれに流されていく。そうやって空を舞い散る桃色と、この仄かに暖かい気温だけが春の証明で。
それなのに、どうしてだろう。僕の心だけが、冬のように冷たい気がした。
その瞬間、僕は振り返って廊下を逆戻りした。どうしてかは分からない。知らないふりをしていた、いつもの感情のはずなのに。
でも、その瞬間だけは。どうしようもなく、彼女の声が聴きたかったのだ。
教室の前まで来て扉を開けようとした時。扉のガラス越しに、机に突っ伏している彼女が見えた。顔は見えないが、言っていたように寝ているのだろう。
僕は少し迷い、扉を開けようとしていた手を引っ込め、さっきと同じように廊下を進んだ。いつもと同じだ。いつものように知らないふりをするだけだ。いつかは忘れるものだ。もう、彼女と会う事はないだろうから。
* * * * *
「……それで、目が覚めたらって感じで」
教室の古い木製の椅子に座った彼女が話し終える。僕はその隣の席でなんとなく当時を思い出しながら「ああ、そう言えばそうだったかも」と呟いた。それに彼女が「え?」と不意を突かれたような反応をする。
「どういう意味?」
「あ、いや、あの後もう一回教室に戻ったら、君が机に突っ伏して寝てたから」
僕は「こんな感じで」と机に突っ伏してその態勢を取る。それを見て彼女は「そう、なんだ」と少し引っ掛かる表情を見せた。
「……どうしたの?」
「いや、えっと、どうして教室に戻ろうとしたのかなって、思ったり」
「……それは、えっと」
例えば、今僕の隣にいるのが、僕と同じように年を取った朱音なら何も気にせず答えられたかもしれない。数年ぶりに再会した朱音だったなら、笑ってあの日を過去形にして話せたかもしれない。
でも、今隣にいるのはあの時の朱音なのだ。だから、それではいけない気がした。彼女にとってはまだ「今」なのだ。大人ぶった僕が、嫌な大人みたいに思い出を語ってしまえば、彼女を傷付けてしまう。
いや、それさえ建前なのかもしれない。僕は安心したかったのだ。あの時のあの選択は間違いではなかったと思いたいだけだ。あの瞬間を肯定したいのだ。結局僕は、自分の事しか考えていない。まだ、終わらせたくないから。
「……ごめん、十年前の事だからさすがに忘れちゃった」
大人とはそういうものなのだ、とでも言いたげに嘘をつく。朱音は対して興味も無さそうに「ふーん」と呟く。大人になる度、言葉にできない何かが少しずつ摩耗していく。嘘をつく事への罪悪感もきっとそうだ。
「それで、どう?」
朱音が突然訊ねる。僕は「え?」と間抜けな声を零した。
「何か、十年前に戻れそうな手掛かりになった?」
「……まあ、それだけじゃさすがに難しいかな」
「だよね」
彼女はそう言って、所在なさげな視線を窓の外に移した。彼女の目に、今日の空はどう映っているだろう。十年前の夏のような青空と、今日という日の夏の青空。違いはあるのだろうか。僕にはもう思い出せないけど。
それからまたほんの少し沈黙が場を支配して、僕は何となく考えたことを口にしてみた。
「とりあえず、学校周ってみない?」
「え? なんで?」
「それこそ手掛かりがあるかもしれないし、何か思い出すかも」
席を立ちあがり、教室の出入り口に向かう。特に考えは無かったけど、朱音は納得してくれたようで「まあ、ここにいても仕方ないしね」と僕に付いてきてくれた。
少し埃っぽい廊下を、二人並んで歩く。まるであの日々をなぞっているようだと、あの日々の延長線のようだと、あまりに身勝手な事を思う。それに自己嫌悪もする。
「震は今何してるの? 仕事とか」
「別に、普通の会社員だよ」
「それだけ?」
「それだけって、それ以外に何て言えばいいか」
「ふーん。じゃあ私、は……」
そこで朱音は一度言葉を止めた。僕は聞き返さなかった。
「……いや、やっぱりいい。聴いていいのか分からない」
「……そうだね。聴かないでいいかも」
少し安堵した自分にまた嫌気が刺した。そのまま質問をされていたら、僕は上手く答えられなかっただろうから。
「こうやって学校歩いてると、やっぱり懐かしいって思うの?」
「うん、まあ」
「煮え切らない返事。なに?」
「いや、僕が懐かしいって思うのは学校そのものじゃなくて、君と一緒にいた時間だから」
「……そっか。そうだよね」
彼女が隣で呟く。僕の間違いでなければ、少し悲しそうに。
「私にとってはついさっきの事なのに、君にとってはもう思い出になるんだよね」
しまったと、率直に思った。ついさっき自分に戒めたのに。僕と彼女では、どうにもならない時間の壁があるのに。簡単に過去形を使ってはいけないのだ。
「どうだろう。僕もまだ──」
「……まだ、何?」
「……いや、何でもない」
でも、それを上手く伝えられない。いや、伝える必要はないけれど。でも、僕の今の想いを、感情を、言葉を。彼女に伝えてはいけないのだ。それはただの自己満足でしかないのだから。
しばらく歩いていると、彼女が足を止めて窓の外を見上げた。彼女に近付きながら「どうしたの?」と訊ねてみる。窓の外では、二匹の夏鳥が青空の下でゆっくりと弧を描いている。
「……私がどうなってるのかって君の口から聴けないのは、怖いからなんだ。私はどこにいるのか、何をしてるのか。今の私が感じてるこの焦燥感から抜け出して、私はちゃんと外に飛び出せているのか」
朱音は窓の外から視線を移し、僕の顔を見上げた。僕らのその距離は、十年前よりほんの少しだけ遠くなっている。
「覚えてるかな? ここで君と話した日の事──」
* * * * *
「八月九日。今日の天気は曇り。窓からなんとなく曇り空を眺めてます。気温は高くないのに湿度は高くてイライラします。あ、鳥が飛んでる。なんかイライラします。えっと、あとあれです。今日も何も無い一日でした」
「うおあ」と声にもならない呻き声を漏らし、ポケットにボイスレコーダーをしまう。襟元をばたつかせ、手で自分の首元を仰ぐ。そんな朱音の様子を見ていたら、空を飛んでいた鳥はいつの間にかいなくなっていた。
「何を鳥にイラついてんの」
「だって、鳥ってなんかムカつくじゃん」
「どこが」
「空飛んでるところとか」
「は?」
視線をまた朱音に戻す。朱音の首筋には、うっすらと汗が浮かんでいた。
「私は、どこか遠くに行きたい。ここじゃないうんと遠くに。分厚い雲の切れ目でもいい。青く澄んだ夏空の向こうでもいい。訳も分からないような柵も焦燥も全部取っ払って、早く自由になりたい。鳥みたいに、空を飛んでみたい」
この気持ちはなんだと、誰かに強く問いかけたくなる瞬間がある。今自分が立っている場所が、言いようも無くむず痒くなる瞬間。自分の居場所はここではないと思いたいだけの瞬間。本当に向かうべき場所が、運命のような場所が世界のどこかにあるんだと信じて疑わない瞬間。
「……その気持ちは、よく分かる。多分、僕もそうだから」
でも結局、そんなものは大人に言わせれば思春期という一言で片付けられてしまうものなのだ。この気持ちを手放す事が成長と言うなら、この痛みすら捨て去る事が大人と言うなら、僕はこのままでいい。あの青空の向こう側を、僕は知りたい。
「君は、いつも何か面白い事を探してる。『何も無い一日』に飽き飽きしてる」
ふと思った事を口に出してみる。特に意味は無い。朱音は「なに、急に」と眉を寄せて訝しんだ。
「鳥になって空を飛べたら面白いのかな」
「……どういう意味?」
またどこからか二羽の鳥がやってきて、空の下で弧を描いて飛び回る。
「僕は鳥を見る度、少し悲しくなるんだ。僕らがこの小さな世界から抜け出したいように、鳥もどこにも行けないまま、存在しない出口を探し続けてるんじゃないかって。僕らが世界中のどこに行けるようになったところで、この気持ちは変わらないだろうなって思う。だって、僕はどこまで行っても僕だから。自分以外の、誰かになりたい」
青空の向こう側なんて本当にあるんだろうか。無くたってそれを求めながら死んでいくのではないか。それは虚しくないだろうか。何も変わらないまま、何も変わらない景色を呆然と眺めるだけの存在なんじゃないか。それはやっぱり、悲劇のように思える。
「……でも私は、やっぱり鳥になりたい」
ぽつりと、言葉が口から零れた事に自分でも気が付かないくらいに小さく、朱音が呟く。
「どうして?」
「だって、君は絶対君のままだもん。どこに行こうと、何になろうと。君はどうしようもなく変われないまま」
朱音は、何も無い空を眺めながら言った。飛び回る鳥を目で追いかけながら。あるいは、羨ましそうに見つめながら。
「だから、私は鳥になりたい。大空を飛べるようになれば、また君を見付けられる。君がこの世界にいる限り、君を探し出す。これだけは忘れないで」
どこにも行けない、何にもなれない、何も変われない。それでいい。それがいい。そうやってありもしないものを探す、そんなゴミのような時間でいい。たったそれだけのものを、僕ら二人で大切にしたい。
きっとなんだっていいのだ。まだ名前の無い感情に名を付けるとか、世界で一番綺麗なものを探しに行くとか。ただそこに、お互いがいる事だけが絶対だ。なら、空の向こうを見上げなくとも、変わらずにいる真下の君を見つけに行こう。その為だけに、悲劇と呼ばれようとも翼を広げよう。
朱音は僕に向かって言った後で廊下を歩き出した。僕もそれに付いて行く。
「君って何かと『これだけは忘れないで』って言う癖があるよね」
何だか気恥ずかしくなって、ごまかすように言った。朱音は「そう? 自分じゃ気付かない」と首を傾げる。
「そのせいで僕は覚えてなきゃいけない事が増えるわけだけど」
「忘れられるのは悲しいから。せめて、君には覚えてて欲しいんだ」
「日記みたいにボイスレコーダーで録音してるのも、忘れないように?」
「そうかもしれない」
これも同じだ。きっと理由なんかどうでもいいのだろう。大事なのは、彼女を忘れない事。それだけだ。
「分かった。じゃあ、僕は全部忘れない。ちゃんと覚えておくよ」
僕が言うと、朱音はこちらを振り向いて微笑んだ。そんな綺麗な微笑みを向けられて、忘れられるわけがない。
「約束だからね」
* * * * * *
「約束しただろ、忘れないって。全部覚えてるよ」
窓の外から、白い光が刺している。朱音の驚く表情を鮮明に照らしている。
「君にとってはつい最近の事が、僕にとっては十年前の出来事だけど。それでも、覚えてる。君が忘れて欲しくなかった事も、ボイスレコーダーに録音した事も。何も忘れたくなかったから」
何も忘れたくなかった。何も置き去りにしたくなかった。何もかもを、大切に抱き留めていたかった。彼女と過ごした一瞬一瞬さえあれば、他に何もいらないから。
少し気まずくなって、朱音から目を逸らす。でも彼女は僕の目を真っ直ぐに見つめ、「じゃあ」と思い立ったように言った。
「君がその約束を忘れてないか、テストしよう」
「なにそれ」
僕が訊ねると、朱音は窓の外を指差して口を開く。
「これから学校を周って、そこで私達が何をしたか、何を話したか、何を録音したか。君に全部話してもらう。それを私が答え合わせする」
「ほら、行くよ」と僕の手を取り、そのまま引っ張って行く。ああ、そうだ。こうやって彼女に手を取られる日々の事を、僕は救いと呼んでいたはずだった。
「別にいいけど、そんな事して何になるの?」
少し戸惑いながら訊ねる。彼女は前を向いたまま、「言ったでしょ」と当たり前のようにこう言った。
「世の中の全てに理由とか意味があると思ったら大間違いだって」
彼女は、「私はどうなってる?」と訊きたかったのだと思う。あるいは、「私と君はどうなってる?」と。僕がそれに対して「聴かないでいいかも」と言ったのは、彼女の質問に答えられる自信が無かったからだ。だって、今の僕はもう、彼女と一緒にはいない。どこに行こうと何になろうと、 僕を見つけ出す。そう言ってくれた彼女はいない。
「その時ちょうど雨が降った。それで君が、レコーダーを濡らさないように必死だった」
「傘忘れちゃってさ。君から傘ぶんどったよね」
「君は僕が風邪をひく事よりレコーダーを優先したんだよ」
十年前の彼女と同じように、僕は今、鳥になりたかった。どれだけの時間をかけても、きっと世界のどこかにいる彼女を見つけ出したかった。なのに、僕はどこにも行けないまま、何者にもなれないまま。翼なんか無い。ただ、どうしようもないような現実が目の前にあるだけ。変わらないものなんて無いという、そんな当たり前が、僕を酷く苦しめる。
「年が明けて初めて蝉の鳴き声をここで聞いた」
「私は夏が楽しみだったのに、君は浮かない顔してたね」
「だって、夏なんて馬鹿みたいに暑いだけじゃん」
「それがいいのに」
もう消える事のない何かを抱きしめたまま、あの頃のままの彼女と、あの時の答え合わせをする。こんな事に、意味も理由も無いのに。あの頃の僕は、意味も理由も無い時間を愛おしく思えたのに。
「君に雪玉を投げられた。痛かった」
「覚えてる。その時の震の人を殺しそうな目が面白くてさ」
「笑い事じゃないだろ」
楽しそうな彼女を見る度、僕はただ苦しくなった。僕と彼女がどんな風になろうと、もう僕と彼女の道は交わらないのに。この瞬間がこの先、彼女をどれだけ苦しめるだろう。そう思う。
「震」
「……なに?」
「楽しいね」
……いや、違う。僕は彼女に苦しんで欲しかった。今も苦しんでいると思いたかった。僕だけが、後悔にすらなり切れない感情を抱いているなんて、許せなかった。何も終わらせられないのが僕だけだなんて、思いたくなかった。
「結局私はイルミネーションなんて好きじゃないんだよ」
「どうして」
「だって、寂しくならない。冬は寂しくなる為の季節なのに」
思い出す度に泣きたくなるような朱音が、目の前にいる。この場所に閉じ込められたいと願った。それ以外は何もいらなかった。
「ここで『あと一か月で卒業だね』って君が言った」
「あれ、そうだっけ」
「僕が覚えてるのに君が忘れてどうすんだよ」
「冗談じゃん。覚えてるよ」
もうどこにも行かないでくれと言ってしまいたかった。なのに今この瞬間も、僕と同じように年を取った朱音がどこかにいるかもしれない。僕を探しているかもしれない。僕を待っているかしれない。ありえないけど、一度そう思ってしまうと焦ってしまう。
「それで結局、卒業式の後も教室にいたんだよね」
「僕も君も、他に居場所がなかったからだ」
「笑える」
過去形なんかじゃなかった。終わらせられなかった。何も思い出になんかできなかった。彼女の姿も、歩き方も、指先も、瞳も、流れる髪も、靴先も、その声も。何も忘れたくなかった。ただひたすらに、切実に、彼女の事が。
「十年前に戻る手がかりを探す、なんて、ただの口実だって分かってるんだ。私はただ、君と一緒にいたい。それだけなのにね」
朱音が少し悲しそうに笑う。ふと気付けば、僕らはまた同じ教室に戻ろうとしている。
「……あ」
教室の扉に手をかけた時、僕は一つ思い出したことがあった。
「なに?」
「いや、ちょっと思い出した事があって」
* * * * *
白いブラウスが、熱気を纏って肌にへばりつこうとする。少し苛立ちながら、教室の扉を開ける。
教室には朱音の他に生徒はいない。当然と言えば当然で、今日は夏休み最終日。学校に来ようと思う生徒の方が少ないだろう。それはいい。問題は、扉を開けた瞬間の朱音の様子が、何かを隠すように明らかに挙動不審だった事だ。
「……何してたの?」
「いや、別に」
「……そう」
言いようのない違和感を覚えつつも、自分の席に戻る。それに気を割けないくらい、とにかく暑かったのだ。夏の終わりは、もう少し切ないものだと思っていたのに。
「……なんだよ」
僕を追う朱音の視線があまりにしつこく、思わず訊ねる。けどやっぱり何かを隠しているように「いや、別に」とはぐらかされた。
「今日は録音しないの?」
暑さと視線をごまかしたくて、適当な事を言ってみる。朱音は「え? あ、そうだった忘れてた」と慌てたようにレコーダーを取り出した。
「八月三十一日、今日の天気は晴れ。えっと、何も無い一日でした」
それだけ録音し、レコーダーをポケットにしまおうとする。僕は「え?」と素っ頓狂な声を漏らしていた。
「それだけ?」
「別にいいじゃん」
「せっかく夏の終わりなんだから、もっとなんかあるんじゃないのかなって」
「別に、何も無かったんだから何も無いでいいの」
心に決めたように言い切る朱音を前に、僕は「あっそ」と言うしかなかった。
八月三十一日。夏の終わりを定義するなら、一つの目安にはなるかもしれない。毎年夏は決まったようにやってきて、こうやっていつも通りに終わっていく。何もしないまま終わっていく。これでいいのだろうかと頭の隅で思いつつも、結局何も無いまま。そうやっていくつもの夏を無駄にしてきたような気がする。
「震はさ、今年世界が終わるかも、みたいな話知ってる?」
朱音が思い立ったように言う。僕は「あー」とどこかで聞いた話を思い出した。
「なんとなく。〝2012 〟って映画もあるよね」
「震はあれ信じる?」
「信じるっていうか、信じたいっていうか、本当に終わるといいなって思う」
「どうして?」
僕は少し考え、自分の中にあるその理由を丁寧に崩して言葉にしてみた。一言で表すなら、「安心」という言葉に繋がるかもしれない。
「理由は沢山あるけど、なんか、色々と楽になりそうだからかな」
人間である限り、名前の無い何かに追われる。何かに縋る。何かに葛藤する。何かに苦しめられる。でも、明日世界が終わるとしたら、それも全て無くなるかもしれない。最後の一日だけは、本当に自由になれるかもしれない。その感覚は、少し気になる。
頭の中でそういう風に整理しつつ、「朱音は?」と訊ねてみる。彼女も僕と同じように少し考えるような表情を見せた。
「私は、世界の終わりってどんな光景なのか知りたい。綺麗な景色だといいなって思う」
「分かる。隕石とか降ってきて欲しい」
僕が言うと朱音は「それは風情が無い」ときっぱり言った。風情ってなんだろう。世界の終わりにそんなものがあるだろうか。
「……世界が終われば、私も変われるかな」
「……どういう意味?」
言いたい事は分かるけど、意図が分からずに訊いていた。朱音は何も答えず、ポケットからもう一度レコーダーを取り出す。
「八月三十一日、今日の天気は晴れ。夏の終わりの空はとても綺麗です。世界の終わりもこんな風だといいなって思います。夏の終わりは世界の終わり、なんて、とても甘美な言葉です。早くそうなってくれればいいのに。何も無い一日も、飽きるような毎日も、全部全部ぶっ壊れればいいのに。世界の終わり以上に面白い事なんて絶対に無いのに」
レコーダーのスイッチを切って、小さく息を吐く。その後で、「震」と僕の名を呼んだ。夏の青空のように、とても澄んだ声で。
「私達は、私と君だけは、どこの誰よりも世界の終わりを望むような人間で居続けよう。絶対に。これだけは忘れないで」
「……そうだね」
そうだといいね。言いかけた言葉を裏に隠し、それと似通ったものを取り出す。朱音はまた、少し悲しそうな顔で笑うのだった。
* * * * *
「あの時、教室で何してたの?」
隣の椅子に座る朱音に訊ねる。朱音は「あの時って?」と少し首を傾げた。
「八月三十一日。僕が教室に入った時、何か隠してたでしょ?」
僕が言うと、彼女は何かを思い出したのか「いや、別に」と露骨に顔を逸らした。
「もういいんじゃない? 今更」
ふと、軽く口から零れた言葉。でもそれは、彼女からすればとても重い意味を持つものだ。僕らの間には、どうしたって壊せない隔たりがある。
「今更って、君にとってはそうかもしれないけど、私にとっては過去形じゃないんだから」
でも、僕の心はまだあの日々に囚われたままだ。過去にできない、ならない。朱音の存在はこんなにも僕を蝕んでいる。こんなにも強い呪いがある。
「……僕だってまだ、何も」
続きを言いかけた時、僕のポケットから着信音が鳴った。「ごめん、ちょっと電話」と席を立って廊下に出る。画面には友人の名前が表示されていた。
「もしもし」
『おい、お前今何してんの』
少し焦ったような口調で訊ねられる。まさかタイムスリップした同級生に会っていた、とも言えない。「別に何も」とごまかす。
『お前まさか高校に入ったんじゃねえの』
「入ってないけど」
『ほんとか?』
「うん」
『本当だな?』
「だから入ってないって」
少し大きな声で嘘を吐く。友人は『だってLine送ったあと返信ないから』と落ち着かない様子で言った。思い出してみれば、こいつに言われてここに忍び込んだんだった。
「ちょっと昨日の事思い出して訊いてみたかっただけ」
『そうそう、お前飲み過ぎて二日酔いでフラフラ入って行ったんじゃないかとか』
「大丈夫だから。二日酔いも平気」
これは嘘じゃない。いつの間にか頭痛は無くなっていた。
『びっくりしたよほんと、急に一気飲みとかするから。らしくない』
昨晩の会話を思い出す。高校の話をして、それで朱音の事を思い出して。だから酒に逃げた。酒に逃げられるのは大人の特権かもしれない。
「だってあれはお前が」
そこでふと、こいつが言った言葉を思い出した。
『学生時代の恋愛ってこういうもんだよ。どうせこの先の人生もずっと後悔し続けるんだろうな』
「……お前が」
『この後悔が消えたらいいのに、って思いながら』
『あ~、タイムスリップとかできたらな~』
まさかと思った。
関係があるのか。いや、関係ないと思うのが普通だ。でも、言いようのない確信。拭い切れない納得。
『……俺が、何だよ』
「……何でもない。もう切る」
『は?』
その言葉を最後に、友人との通話を切る。
一つ息を吐いて、教室へと戻る。朱音は変わらず自分の席に座っていた。何か会話をするわけでもなく、その隣に腰を掛ける。
訊ねるべきだろうか。どんな言葉をかけようか。そもそも僕は、彼女に元の場所へ戻って欲しいと思っているだろうか。数多の感情が僕の中で渦を巻いている。
そんな僕を見て何か思う事があったのだろうか。朱音は僕に「ねえ」と声をかけた。とても優しい声、言い換えれば、何かを諦めたかのような声音で。
「震ってさ、後悔とかした事ある?」
「僕は別に──」
ないけど。そう言いかけ、言葉を止める。
朱音と過ごした日々は間違いなく、僕にとっての救いだ。今だってそうだ。あの記憶さえあれば、この先も後ろを向きながらでも生きていけると信じている。
でも一つだけ。どうしても引っ掛かる記憶がある。三月九日。卒業式の後。朱音と別れて、教室を出て、でも教室にもう一度戻って。
もしもあの時、朱音が眠っていなかったら。あの時、扉を開けて朱音を起こしていたら。僕は何をしていただろう。何を言いたかっただろう。答えは分かり切っている。でも、時間を巻き戻せたとして、僕はそうするだろうか。
「……いや、分からない。あれが後悔なのかどうかも」
後悔と呼ぶのは簡単だ。でもそれは、あの日々を否定する事にならないだろうか。もしそうなら、やっぱり後悔とは呼びたくはない。あれでよかったのだと、自分に言い聞かせていたい。
「私はね、たった一つだけ後悔してる事があるの」
朱音の言葉を聴いて、少しだけ悲しくなった。彼女ですら、何かを後悔する事があるんだと、勝手な事を思う。
朱音はポケットからレコーダーを取り出し、スイッチを入れる。録音じゃない。再生だ。
「言おうか迷ったんだけど、私──」
『三月九日、今日の天気は晴れ。二度目の録音です。……言えなかった。今日しかなかったのに。今日じゃなきゃ駄目だったのに。私が今までに伝えた事、何を忘れてもいい。だけど、私の事だけは、忘れないで欲しい。私もこの先、君の事だけは何があっても忘れないからって。そういう風に言いたかったのに。私は、震が──』
「あの日、寝てたんじゃなくて泣いてたの」
「……どうして」
それは、本当にたくさんの意味を込めた「どうして」だった。彼女がそれをどういう風に捉えたかは分からない。でも朱音はちゃんと、僕の疑問に応えてくれた。
「この後悔が消えたらいいのにって思った。今すぐに時間が戻ればいいのにって。まさか、逆に時間が進むとは思わなかったけど」
また、諦めたように悲しく笑う。僕は何を言えばいいのか分からなくて、何を言っても間違いな気がして、ただ口を閉ざした。
「ねえ、震が教室に戻ってきたのってどうして? 私が起きてるって知ってたらどうするつもりだったの? それとも、それすらもう、君の中では思い出なの?」
「違う」
強く断言する。思い出なんかにしてやるものか。まだ、僕の中で全部生きてるんだ。
「思い出なんか一つも無い。過去形にした事なんて一つも無い。後悔なんか一つも無い。だって、あの時言えなかった言葉も、今この瞬間になら君に言えるんだから」
「……じゃあ言ってよ」
少し震えた声で朱音が言う。思わず顔を逸らす。分からないけど、彼女の涙だけは見てはいけない気がした。
「……言えない。それを言うのは、言うべきなのは、君だから。君がその後悔を消さない限り、多分君は戻れない」
理由とか理屈とかはどうでもいい。でも多分、タイムスリップと呼ぶべきこの現象は、後悔がトリガーだ。僕も朱音も、どうしてかそれを薄々感づいていた。でも、見て見ぬふりをしていた。だって。
「……別に、消さなくてもいいって思っちゃうんだ。このままここにいてもいいかなって思っちゃうんだ。だって、また君に会えたんだから」
思わず頷きそうになる。振り向きそうになる。声をかけそうになる。
「でも、やっぱり駄目だよね。このままだと私は、十年後に君と一緒に笑えない。変わらず君といられるように、変わらなきゃいけないんだ」
彼女がいる方向から、音がした。カチカチ。レコーダーのスイッチを入れる音。そして多分、僕らの別れの音。
「十年後の七月四日。今日の天気は晴れ。数分前伝えられなかった言葉を、十年越しの君に伝えます。 何も無い一日でよかった。意味も理由も何も無い世界でよかった。私はただ、君と一緒にいられれば、それ以外は何もいらなかった。震、忘れないで。私は、君がずっと好きです。他の何を忘れても、これだけは忘れないで。……またね」
蝉の鳴き声が聞こえる。風が空を切る音がする。教室から、人の気配が無くなったのが分かる。
「……そんなの、僕だって同じなのに。僕だってそうそう思いたいのに」
なぜだか、無性に苛立っていた。何に、と言われても分からない。暑さかもしれない。自分かもしれない。現実かもしれない。世界かもしれない。分からない。とにかく、死にたいくらいに苛立っていた。
力任せに、自分が使っていた席を思い切り蹴飛ばす。大きな音を立てながら倒れる。
その机の中から、一枚の紙切れがひらりと落ちた。ゴミにしては少し大きく、人の手が加えられたように丁寧に折り畳まれている。拾い上げ、広げてみる。
「朱音 十年後、始まりの場所でまた君と会えますように」
——その瞬間に、僕はもう走り出していた。
『七月四日。今日の天気は晴れ。私は今、 何となく屋上にいます。とにかく暑い。屋上なら少しはマシかなと思って——』
扉を乱暴に開けて教室を飛び出す。
『七月十日。今日の天気は雨。珍しく土砂降りの日です。急な雨で傘を忘れました。とことん最悪の一日です──』
陽を返すリノリウムの床を強く蹴る。
『八月九日。今日の天気は曇り。窓からなんとなく曇り空を眺めてます。気温は高くないのに湿度は高くてイライラします。あ、鳥が飛んでる。なんかイライラします——』
長い廊下に鋭い足音が強く響く。
『八月一日、今日の天気は晴れ。夏が始まりました。蝉がうるさく鳴いています。二か月の命に──』
階段を一段飛ばしで駆け上がる。
『八月三十一日、今日の天気は晴れ。夏の終わりの空はとても綺麗です。世界の終わりもこんな風だといいなって思います。夏の終わりは世界の終わり——』
踊り場で転びそうになる。
『十一月三日、今日の天気は雪。そうです、雪が降りました。震に雪玉をぶつけたらマジで 怒ってました──』
不快な汗が顔を伝う。
『十二月二十四日。今日の天気は晴れ。どこもかしこもイルミネーションだらけです。クリスマスなんて——』
息が切れて胸が締め付けられるように痛む。
『二月九日、今日の天気は曇り。卒業式まで一か月を切りました。もう私達が高校生でいられる時間も──』
構わず走り続ける。
『三月九日、今日の天気は晴れ。言わずもがな卒業式の日です。ずっと立ちっぱなしで足腰が痛い。疲れた。震もしんどそうにしてます——』
夏の香りがする。
『三月九日、今日の天気は晴れ。卒業式の後で教室にいたら、いつの間にか学校から人が消えていました。さすがの私でも違和感を——』
君の声を思い出す。
『十年後の七月四日。今日の天気は晴れ。数分前伝えられなかった言葉を、十年越しの君に伝えます——』
屋上へと続く扉を開ける。
『震、忘れないで。私は、君がずっと好きです。他の何を忘れても、これだけは忘れないで。……またね』
ただ、青いとしか言えない空が広がっている。他には何も無い。夏風が優しく吹いている。
少し広く感じる屋上の真ん中に、ぽつりと何かが置かれている。近付いて見ると、少し古い型のボイスレコーダーだった。見間違うはずがない。彼女が使っていたものだ。
録音履歴の一番上に、今日の日付がある。少し震える手で、再生ボタンを押す。
『七月四日。今日の天気は晴れ。今私は、なんとなく屋上にいます。もう廃校になってしまった私の母校です。
ふと、十年前の不思議な出来事を思い出しました。卒業式の後、私は十年後にタイムスリップしたのです。つまり丁度今、どこかに十年前の私がいるかもしれません。あるいはもう十年前に戻った頃でしょうか。もう断片的にしか思い出せません。全てはただの思い出になってしまいました。
あの頃の私は、あまりに愚直で未熟な恋をしていました。何も無い人生に訪れた彼の存在を、今になってふと想います。私と彼の二人なら、この世界のどこへだって飛べるのだと疑っていなかった。どこにいようと、何になろうと、番のように二人でいられると思っていた。例え世界の終わりが来ようと、その最後の瞬間まで共にいられると祈っていた。例え世界が終わるとしてもその瞬間、私はようやく全てを手に入れられると思った。愛の証明とか、心の場所とか、言葉の輪郭とか。そういう、いくら考えてもしょうがないようなものの答えが分かると思った。どうしようもなく救われない世界で、私と彼だけが救われると思った。たかが世界の終わりと言えてしまうくらい、彼と共にいたかった。
意味も理由もいらないと、昔彼に伝えました。私が今、ここに立っている事にもやっぱり意味も理由もありません。ふと、過去形になったあの日々を思い出したから。それくらいの理由でいいのです。
十年前、机の中に私の想いの丈を記した手紙を入れました。あれを彼が読んだのかどうか、私には分かりません。ですが、彼がここにいないという事はそういう事なのでしょう。
十年前に出会った彼は、今もこの世界のどこかで生きている彼は、もう変わってしまった。多分、私も同じです。変わらないものなんて無いという、当たり前の事実があるだけです。
あるいは、少し時間を置いて彼はここにやってくるのでしょうか。それは嫌だなと少し思います。もう彼にはここに来ないで欲しい。十年前の私を見送った後で、悪い夢を見たようだと思いながらここを去って欲しい。もう、全てを終わらせてさよならして欲しい。強く、そう思います。
何も無い人生でも、ただ彼がいればそれだけでよかった。何を忘れても、私の事だけは忘れないで欲しかった。十年後、始まりのこの場所で君と会いたいと願った。全ては過去形になりました。私も君も変わりました。懐かしい思い出になりました。私はもう、彼に会いたいとは思いません。
これが最後です。彼に伝えたい言葉を、 誰にも伝わらない記録としてここに残します。
ねえ、震。君の事を思い出す度、泣きたくなるくらい、悲しくなるくらい、私はただ、君が好きでした。私はもう、君を忘れます。だから君も、私の事だけはどうか』
カチカチ。レコーダーのスイッチを切る音。
僕らの周波数が、すれ違う音。
『どうか、忘れてください』
ヨルシカ - 声
添付されてるシナリオと合わせてご一読ください。
予定主題歌 ヨルシカ / 声
カチカチ。
ラジオのダイヤルを回す音。そして、周波数を合わせる音。
『七月三日。今日の天気は晴れ。梅雨が明けた今日は各所で晴れ模様が見られ、洗濯物のよく乾く日となりました。今週一週間の予報を見てみますと──』
窓の外を見る。時刻は午後十時半を少し回ったところ。言われてみると確かに、夜空は深く澄んでいる。青空の色を忘れてしまいそうなほどの星が瞬いている。視界のピントをずらすと、同窓会という名目で缶ビールを呷る友人達の姿がはっきりと映っている。
人の声が好きだった。一時的にでもこの心の穴を埋められるなら、誰の声でもよかった。
人が最初に忘れるものは、人の声だという。だからというわけでもないけど、誰かの声を覚えておきたいと思うようになった。でも。
「──で、お前はどうなんだよ。おい、震」
「え? なに?」
友人に肩を揺さぶられて意識が戻る。その拍子に握っていた缶ビールから中身が少し零れる。
「ぼうっとすんなよ。まさかもう酔ったの?」
「ごめん、ラジオ聴いてた。いい声だなって思って」
「ラジオよりこっちの話聞いとけよ。なんか面白い話ないのかって」
缶ビールに口を付ける。別に冷たくもない発泡酒の苦みが口に広がる。はっきり言って美味しくはない。
「別に何も無いよ。やり甲斐も無いまま仕事してるし、生き甲斐も見付けられないまま生きてる」
いつからだっただろうか。忘れてはいけないものを、忘れていくようになったのは。何も無い一日とか、あの日の青空とか、何かの大それた意味とか理由とか。そういうものを手放した瞬間が僕にもあったらしい。それすらももう忘れてしまった話だけど。
「なんかお前、卑屈になってね?」
「震はずっとこういう奴だったぞ」
「そういうのじゃなくてさ、せっかく集まったんだし思い出話しようぜ。な? 何かあるだろ?」
「……思い出って」
人が最初に忘れるものは、人の声だという。だからというわけでもないけど、誰かの声を覚えておきたいと思うようになった。でも。
『七月四日。今日の天気は晴れ。私は今、何となく屋上にいます──』
あの瞬間の、あの彼女の声だけは、今も僕を離してくれないままだ。
「そうそう、俺未だに分からないんだけどさ、一時期机にゴミ入れられてたんだけど、アレっていじめ?」
友人の一人が思い出したように話す。僕は手持ちの缶が空になり、新しい缶ビールのプルタブを起こした。
「それアレじゃねぇの? 好きな人と付き合えるってやつ」
「何それ」
「好きな人の机に自分の名前を書いた紙入れて、しばらく見つからなかったら両想いになる、みたいなの。あったよな?」
「は? 俺ろくに見ずに捨ててたんだけど」
「うわ、もったいねえ。付き合えてたかもしれないのに」
「それ高三の時の話だろ? 運が良ければ結婚だってしてたかも」
「うわぁー! 早く結婚してえー!」
僕がいなくても楽しくやってただろうなと思いながら、テーブルの上のお菓子に手を伸ばす。自分はここにいなくてもいいなという疎外感とか、自分がここにいるからこそ生まれる罪悪感とか。人生はそういうものの繰り返しらしい。ラジオの音量を上げる。
『さて、続いては大人気コーナー、恋のお悩み相談室です! 今回もたくさんのお便りをありがとうございました! お便りを読ませて頂いて、私も高校生に戻りたくなっちゃいました! あ~、タイムスリップとかできたらな~』
「まあでも」
笑いが少し治まり、余白に挟み込むように友人がぽつりと呟く。
「学生時代の恋愛ってこういうもんだよ。どうせこの先の人生もずっと後悔し続けるんだろうな。この後悔が消えたらいいのに、って思いながら」
その瞬間、僕は開けたばかりの缶ビールを一気に流し込んだ。冷えてもいない、美味しくもないビール。友人が「こいつマジか」とはやし立てる。
「おい、震がやる気だぞ」
「いけいけ! 全部飲め!」
「一気! 一気!」
後悔はきっと、全てを過去形にした人間の特権なのだと思う。だから、何も終わらせられない僕のこの感情は、きっと後悔ではない。じゃあ一体、この感情はなんなのか。未だに分からない。彼女を思い浮かべる度、彼女の声を思い出す度、僕はただひたすらに、どうしようもなく。
『震』
どうしようもなく、泣きたくなる。
* * * * *
『俺も楽しかった。また集まろうぜ。二日酔いお大事に』
友人からのメッセージにスタンプを送信し、携帯をポケットにしまう。無理な飲み方をしたせいか少し気分が悪い。
体調の悪い日に浴びる直射日光ほど憎らしいものは無いと思う。空を見上げてみると、文字通りに一点の曇りも無い青空が遠く澄んでいる。こういう時、夏が嫌いになる。高校時代の僕は夏が好きだったはずなのに。いや、「彼女」と共に過ごした夏だったからこそ、そう思えてしまうのだろうか。
昨日の同窓会で変な話をしてしまったせいか、そういうどうでもいい事を考えてしまう。いい加減終わらせないといけないのに。いい加減過去形にしなければならないのに。二日酔いで回らない頭が、そういう自責の念だけはくっきりと浮かび上がらせる。
家に帰って冷たい水を飲もう。もう少しだけ睡眠を取ろう。そうやって雑念を振り払おうとした時。ふと、自分の歩いているこの場所が高校時代の登下校の道である事に気が付いた。
友人の家から僕の家までは、この道を歩かなければならない。もうこんな道、歩く事はないと思っていたのに。回らない頭が今度は痛みを連れてくる。
しばらく歩き、高校の前にまで辿り着く。何事もなく通り過ぎようとしたのに、視界の隅に校舎を捉えた瞬間、僕は思わず立ち止まっていた。
『この後悔が消えたらいいのに、って思いながら』
昨晩の友人の言葉がフラッシュバックする。その時、僕は妙な事を思い付いた。ポケットにしまったばかりの携帯を取り出し、友人に再度メッセージを送る。
『あのさ、昨日高校時代の話したじゃん。卒業生って中に入れたりしないかな』
『高校って、俺の家の近くの?』
返信はすぐに来た。『それそれ』と肯定する。
『覚えてないのかよ。老朽化とかで高校の住所は移動しただろ。その校舎自体はもう使われてないぞ』
確かに、校舎をよく見ると年季が入っているというか、どうにも人の立ち入りが感じられない。窓ガラスや壁はひび割れ、雑草があちこちで茂っている。
つまり、今は誰も人がいないわけだと、痛む頭でそんな事を考えた。
『犯罪者になってもいいなら入れるかも、なんてな。 ……入らないよな?』
友人のメッセージを確認し、スマホに有線イヤホンを挿す。ラジオを聴けるアプリを立ち上げ、またポケットにしまった。
『七月四日、今日の天気は晴れ。観測図から梅雨前線が消え、日本全土での夏入りとなりました。日焼け対策をし、熱中症には充分お気を付けください。また、明日からは急激に気温が──』
周囲を少し確認し、素早く校門を飛び越える。
敷地に足を着地させた瞬間、数年前の幻影を鮮明に見てしまった。あの日々の続きをなぞるかのように。ともすれば、僕は学ランを着ているのではないかと錯覚してしまうほどに。
全部覚えている。ここは少し段差があって転びやすくなってるとか、ここは窪んでいて雨の日には水溜まりができるとか、あそこには名前も知らない花が一本だけ咲いているとか。三年間で目に焼き付けた光景が、そこにある。昨日の飲み会で話した事を思い出すよりも先に思い出せる。
僕が今やっている事は、もちろん立派な犯罪だ。どうしてこんな事をしているのか、僕にも分からない。昨日の会話が原因かもしれないし、二日酔いで頭が回らないという言い訳かもしれない。でも、そんなのは全部詭弁だと分かっている。どこまで行ったって、僕の欲しいものは、求めているものはたった一つだ。世界でたった一つだけの、あの空気の振動だ。
『ねえ、震』
校舎の扉には鍵がかかっておらず、すんなりと開ける事ができた。こうなるともう自制は効かないと自分で分かっていた。誰の気配も無い、埃っぽい校舎に足を踏み入れる。まずは昇降口からすぐの階段を上る。一階、二階、三階。三階に着いて、突き当りの廊下を真っ直ぐ進む。
機械、というのも違う。僕の中の本能みたいなものが足を動かしていた。つまり、僕が向かっているのは僕が通っていたクラスだ。
長い廊下の先、もうすぐで目的地というところまで来た時だった。
「……は、……にこ、……な」
イヤホンの外から、人の声のような音が聞こえた気がした。まさか、そんなはずはない。いや、ここを管理している関係者かもしれない。見つかったらどうやって言い訳しようか。そんな事を考えながら歩き、教室の前に辿り着く。そして、イヤホンを外した瞬間。
「三月九日、今日の天気は晴れ。卒業式の後で教室にいたら、いつの間にか学校から人が消えていました。さすがの私でも違和感を覚えてます。しかもなんか蒸し暑いし。意味が分かりません。とりあえず家に帰って──」
教室の中から、声がしたのだ。
間違いじゃなければ、……いや、間違いじゃない。その声は、僕がこの数年で嫌と言うほど反芻した声だ。この世界で、この世で、たった一つだけの空気の振動だ。数年ぶりに、鼓膜が同じ揺れ方をしているのだ。
痛いほどに鳴る鼓動を無視し、教室の扉を開ける。
教室の中心にいたのは、制服を着た一人の女子生徒だった。
「……朱音」
「……震?」
カチカチ。
彼女がレコーダーのダイヤルを回す音。
そして多分、僕らの周波数が重なる音。
* * * * *
生まれて初めて地下から飛び出した人間が、本から得た知識だけで描いたような「夏」の青空の日。校舎には熱気が充満していて、僕はたまらず立ち入り禁止の屋上へ避難しようとしていた。
「七月四日。今日の天気は晴れ。私は今、 何となく屋上にいます──」
扉を開けようとした時、向こう側から声がしたのだ。この高校に入学してから二年間、屋上は僕一人が使ってきたお気に入りの場所だった。
思わず溜め息を吐く。聞くに女子生徒の声らしかった。もうここは使えないかもしれない。また新しく一人になれる場所を探しておこう。そう思いながら、せっかくだからと扉を開ける。
屋上は綺麗な正方形の形をしていて、それを少し背の高い柵が囲んである。そのど真ん中に、一人の女子生徒が座り込んでいた。僕に背を向ける形だ。
「とにかく暑い。屋上なら少しはマシかなと思って来てみたのにちっとも涼しくありません。なんなら校舎より暑い気がする──」
そこまで言った時、人の気配に気が付いたらしい。女子生徒は体育座りの態勢のままこちらを振り向いた。
容姿には取り立てて特徴の無い女子だった。どこにでもいるような、あるいはどこかで見た事があるような、そんな感じだ。強いて言うなら、少し切れ長の目が睨みつけるような鋭い視線を送っているくらいだろうか。
「……なに?」
僕を睨みながら、彼女が言った。
それが、初めて聞いた彼女の声だった。
その声は、まるで僕の人生のアナウンス担当かのように僕の中に馴染んだ。神様が言葉を発するとすれば、きっとこんな声なのではないかと思った。
「いや、何してるのかなって思って」
「何って、見れば分かるでしょ。録音」
「それは分かるけどさ」
彼女は右手に細長い機械のようなものを握っていた。ボイスレコーダーか何からしい。それをポケットにしまいながら、「君こそ」と僕に言葉をかける。
「屋上まで何しに来たの? ここ立ち入り禁止だよ?」
「ここなら風が吹いて少しは涼しいかなって思って」
「残念だけど期待外れ。全然」
「そうみたいだね。聞こえてたよ」
僕が言うと、彼女は「うわ」と言って露骨に顔を顰める。
「聴いてたの? 趣味悪いよ」
「聴いてたんじゃなくて聞こえてたんだって」
「同じじゃん」
彼女が苦笑いするように呟く。「聴く」と「聞く」の間にはそれなりの距離があると思うのは僕だけだろうか。
後ろに手をつき、彼女は青空を見上げた。何も無い青空だ。世界全部が青色で満たされればいいのにと祈ってしまうような空だ。こんなにも近くて、こんなにも遠い。
「君、名前は?」
「……震。なんで?」
「盗聴犯の名前くらいは覚えておこうと思うって。あ、私は朱音。忘れないでね」
彼女は僕を見てほんの少しだけ口角を上げた。今度は僕が顔を顰める番だった。
「何を録音してたの?」
ふと気になって訊ねる。彼女はボイスレコーダーの入ったポケットをさすりながら「別に」とぶっきらぼうに言った。
「その日あった事とか。何も無い日だったら『何も無い一日でした』で終わりだし」
「何の為に?」
「意味なんか無い。日記と同じだよ」
「じゃあ日記でいいじゃん」
「ごちゃごちゃうるさいなあ」
僕の言葉を遮るように言った彼女は、突然立ち上がるとおもむろに僕との距離を詰めた。
「あのね、世の中の全てに理由とか意味があると思ったら大間違いだよ。人間が生まれてくるのに理由も意味も無いのと一緒。私が自分の声を録音してる事に何かを見出そうとするだけ無駄。これだけは忘れないで。分かった?」
彼女はそう言って僕の顔を指差す。
全てに理由や意味があるわけではない。理由や意味も無く、見つけられずにのうのうと生きているのだからそうだろう。彼女の言葉には妙な説得力があるような気がした。いや、それすらも彼女の声がそうさせるのだろうか。
僕がゆっくり頷くと、彼女は「よし」と初めてちゃんと笑った。切れ長の目が細くなり、印象が変わるくらい可愛らしい笑顔だった。
「じゃあ私は戻るから。君も早く戻りなよ」
そう言って手を振り、屋上から出て行こうとする。僕は力なく「あ、うん」と呟く。
「あ、そうそう」
扉に手をかけた彼女が、何かを思い出して振り向いた。僕を指差し、口を開く。
「『何も無い一日でした』って録音するのにはもう飽きてるの。何か面白い事があったら教えてね。これも忘れないで」
それだけ言い残し、もう一度手を振って今度こそ屋上から出て行く。
屋上には何も無い。ただ耳が痛いくらいの静寂だけが取り残されていた。
* * * * *
初めて彼女を見た時と同様、切れ長の鋭い目が僕を睨んでいる。彼女が本当に朱音であるか疑問だったし、目の前の彼女も僕が本当に僕なのか自分を疑っている。お互いにそうだっただろう。
「……君、誰?」
とりあえず、僕の方から声をかけてみる。彼女は「こっちのセリフ、です」と、とりあえずといった感じで敬語交じりに言った。
「そっちこそ誰? 震? なんか老けた?」
向こうは僕の名前を知っている。彼女が朱音である事は間違いないらしい。でも、数年前の姿をした朱音がここにいる事はもちろんおかしい。あの時間で脳に焼き付けた彼女についての記憶と、あの日々の朱音がここにいるという非現実。僕はどちらを疑うべきなのだろう。
その時、僕の脳裏に誰かの声がよぎった。どうしてこのタイミングだったのか分からない。それでも、つい最近聞いたような気がする誰かの声が鳴ったのだ。
『あ~、タイムスリップとかできたらな~』
まさか。そんな事があるだろうか。いやでも、回らない僕の頭ではそれ以外には思い付かない。
目の前にいる非現実を見つめる。「なに、ですか」と警戒したままの朱音に、僕は言葉をかけた。
「僕らが出会った日にちと場所、言える? あと、どんな出会い方だったか」
「何で」
「いいから」
少しだけ強い口調で促す。朱音は眉をひそめ、思い出すように「えっと」と答えを口にした。
「七月四日、屋上。盗み聞きがどうとかって話した。いや、貴方が震だと仮定した上でだけど」
大きく息を吐く。間違いない。目の前にいるのは朱音だ。だけど、数年ぶりの再会というわけではない。どういう事か、あの日々のままの、高校三年生の朱音。つまりはやはり、タイムスリップをしたという事。
「一応本当みたいだね。納得するしかなさそうだ」
僕が言うと、朱音は「いやいや」と少し焦った様子で言った。
「ちょっと待ってよ、私はしてないんだけど。本当に震なの?」
「まあ」
「まあって何よまあって。なんか証明してよ」
今度は苛立ったように言う。確かに彼女の言う事も一理ある。どういうわけか、目の前には成長して少し老けたクラスメイトがいるのだ。そういう反応にもなるだろう。けれど。
「証明って……」
急に言われても、そんなもの用意しているはずがない。一応財布はある。免許証を見せるか? いや、そういう話でもないだろう。理論ではなく、本能で納得しなければ気が済まないのだ。つまり、僕が僕であると、心で理解したいのだ。
「……君の名前は、朱音だ」
僕が言うと、朱音は眉をひそめて「なに今更」と訝しんだ。僕はそれに「まさか、忘れたの?」と続ける。
「君が言ったんだろ。朱音って名前を、 忘れるなって」
そう言うと彼女は少し驚いたように目を見開いた。どうやら納得したらしい。「まあいいや」と息を吐く。
「じゃあ本当に震だとして、老けてる理由は? あと急に暑くなった理由。まさかタイム」
「タイムスリップだろうね。理由は知らないけど」
また彼女の言葉を遮るようにして断言する。朱音は「本気?」と少し馬鹿にするような言い方をした。僕が老けているのは認めるけど、タイムスリップしたとは信じられないらしい。
とりあえずと思い、ポケットからスマホを取り出してそこに表示されている日付を見せる。しかし朱音は「なにこれ」とスマホを人差し指と親指で摘まんだ。そうか、まだスマホも珍しい時代だったか。
僕はスマホを操作し、さっきまで聴いていたラジオのアプリを開く。そして有線のイヤホンを外して、スピーカーでボリュームを大きくした。
『……やっぱり十年前と言えばあれですね。ノストラダムス、じゃなくて、えっと、忘れちゃいました。でもほら、地球滅亡説があったじゃないですか。〝2012 〟なんてSF映画もあったくらいですよ。私もどうせ地球が終わるなら宿題とかしなくていいやって思ってたらめちゃくちゃ学校始まるっていうね』
「……マジ?」
朱音が信じられないものを見る目と声で訊ねる。僕が小さく頷くと、近くにあった席に座って頭を抱えた。僕も同じ気持ちだ。
それからしばらくは、お互いに何か言うでもなく無言の時間が続いた。でも、このままで事態が進展するわけでもない。僕は一つ咳ばらいをし、彼女に短く訊ねる。
「えっと、どうする?」
「どうするって、私に訊かれても」
「……ごめん、言い方を間違えた。君はどうしたい? 十年前に戻りたい?」
彼女はずっと難しい顔をしていたが、僕が訊ねると「まあ」と小さく深呼吸をした。
「ここにいてもしょうがないし、戻らないといけないよね」
「じゃあ戻る方法を考えよう」
「どうやって?」
「それが分からないから考えようって言ってるんだよ」
現状を整理する必要がある。今の僕と今この場所は、僕の時代だ。となれば、イレギュラーなのは朱音だけ。彼女さえ元の時代に戻ればいい。彼女が戻るべき時間を把握しておいて損はないだろう。
「とりあえず、ここに来るまでの事を教えてよ。卒業式の後だっけ?」
僕が訊ねると、朱音は小さく頷き、僕に思い出させるようにあの日の事を語った。
「もしかして覚えてない? 卒業式の後、 私達──」
* * * * *
「三月九日、今日の天気は晴れ。言わずもがな卒業式の日です。ずっと立ちっぱなしで足腰が痛い。疲れた。震もしんどそうにしてます」
「してない」
「ちょっと邪魔しないでよ。……えっと、なんだっけ」
朱音は頭をガシガシと掻いて、「忘れた。もういいや」と投げやりにボイスレコーダーをポケットにしまった。
「最後の日なのにそんな適当でいいの?」
「疲れたって言ったでしょ。もう録音する気力も無いの」
「もったいない」
なんとなく口を出た「もったいない」。それはもちろん、今日が高校生活最後という意味を含んでいる。けど、それがなんだとも同時に思う。一分一秒が最後で、今この瞬間が最期なのはいつだってそうで。でも、それを分かっていても時間をゴミみたいにしか扱えない。それがまるで人間の証明だとでも言うように。「もったいない」なんてのは、人間から外れるほど時間を効率よく消費する奴の使う言葉かもしれない。
高校生活を終えて何者でもなくなった僕らは、それでも静かな教室で時間を無駄遣いしていた。間違いなく、悲しいくらいに人間だった。
「……もうこれで終わりなんだね」
朱音が誰に言うでもなく、独り言のように言う。僕は返事をするか迷って、小さく「そうだね」となんとなく同意した。それと同時に、どうでもいい野暮な疑問も浮かんだ。
「楽しかった?」
「何が」
朱音に逆に訊ねられ、別に大した事を考えていなかった僕は「いや、なんとなく」と呟く。
「学校生活っていうか、人生って言うか。ほら、何も無い一日には飽きたって、 君が言ってただろ」
「……よくそんな事覚えてるね」
「忘れるなって言ったのは君だ」
「そうだっけ」
朱音が少し笑いながら言う。そして少し考えるような間を置いた後で、「そうだね」と自分に、あるいは誰かに言い聞かせるように言った。
「空は飛べなかったし、世界は終わらなかった。けどまあ、それなりに楽しかったよ」
劇的な何かがあったわけじゃない。ただ時間は過ぎ去った。でも、たったそれだけの事が僕らにとっては全てだった。彼女と出会ったあの瞬間、僕の世界は間違いなく変わった。彼女と過ごした日々が、僕にとっての世界だった。そういうものを一々言葉にしたかった。でも、どこをどれだけ探したって、それに相応しい言葉は無いのだろう。
「……僕も程々に楽しかったよ」
だから結局、こんな風な言い方しかできない。それが少し悔しくもあって、少し嬉しくもある。これだけの言葉に、精一杯の僕の感情を詰め込む。
朱音にそれが伝わったかどうか分からない。彼女はいつもの調子で「ふーん」というだけだった。それでよかった。伝わらなくてもいい。言葉という入れ物に、僕の世界全部を詰め込んで君にあげよう。それが、僕に最後にできるせめてもの信仰だ。
「……じゃあ、僕はそろそろ帰ろうかな」
しばらく続いた沈黙に耐えられず、先に音を上げる。今まではこんな事なかったのに。
僕が立ち上がると、朱音は座ったまま「うん」と小さく零した。
「君はどうする?」
「私はもう少しここにいるよ。少し眠って帰ろうかな」
「そっか」
少し迷った。このまま帰っていいのだろうか。多分、彼女と会う事はもうないだろう。せめて何か言葉をかけた方がいいと少し思う。でも、無駄な言葉を重ねてしまうくらいなら、静かに別れるべきだとも思う。
「ねえ」
そんな葛藤をしていたら、彼女が先に口を開いた。僕は「え?」と少し間抜けな声を出す。
「えっと、これも忘れないで欲しいんだけどさ。その、私」
そう言って彼女は座ったまま、自分の指先だけを見つめていた。
発した言葉が違和感になるのに充分な沈黙が訪れた後、意を決したように一度僕の顔を見つめ、結局は「いや」と迷いながら首を横に振る。
「何でもない」
「なんだよ」
「何でもないってば。眠たくて忘れちゃった」
今の様子を見ていれば、何でもない事くらい僕にでも分かる。何か言いたかったのだろう。でも、彼女は口を閉ざす事を選んだ。なら、そうするべきなのだろう。僕は「そう」と気持ちを呑み込む。
「えっと、じゃあ」
「……うん。じゃあね、震」
「さよなら。朱音」
それで、僕は教室を出た。多分、かけるべき言葉はもっとあっただろう。やるべき事はもっとあるだろう。それでも、いつだってこうやって生きていくのだ。それが人間だから。今に限った話じゃない。
廊下を進み、ふと窓の外を見る。空は夏のように晴れている。
そこから見える屋上を眺め、世界が変わったあの瞬間を思い出した。彼女と出会った日を。彼女の目はいつも、秋のように涼し気だった。
強い風が吹いて、桜の花弁がそれに流されていく。そうやって空を舞い散る桃色と、この仄かに暖かい気温だけが春の証明で。
それなのに、どうしてだろう。僕の心だけが、冬のように冷たい気がした。
その瞬間、僕は振り返って廊下を逆戻りした。どうしてかは分からない。知らないふりをしていた、いつもの感情のはずなのに。
でも、その瞬間だけは。どうしようもなく、彼女の声が聴きたかったのだ。
教室の前まで来て扉を開けようとした時。扉のガラス越しに、机に突っ伏している彼女が見えた。顔は見えないが、言っていたように寝ているのだろう。
僕は少し迷い、扉を開けようとしていた手を引っ込め、さっきと同じように廊下を進んだ。いつもと同じだ。いつものように知らないふりをするだけだ。いつかは忘れるものだ。もう、彼女と会う事はないだろうから。
* * * * *
「……それで、目が覚めたらって感じで」
教室の古い木製の椅子に座った彼女が話し終える。僕はその隣の席でなんとなく当時を思い出しながら「ああ、そう言えばそうだったかも」と呟いた。それに彼女が「え?」と不意を突かれたような反応をする。
「どういう意味?」
「あ、いや、あの後もう一回教室に戻ったら、君が机に突っ伏して寝てたから」
僕は「こんな感じで」と机に突っ伏してその態勢を取る。それを見て彼女は「そう、なんだ」と少し引っ掛かる表情を見せた。
「……どうしたの?」
「いや、えっと、どうして教室に戻ろうとしたのかなって、思ったり」
「……それは、えっと」
例えば、今僕の隣にいるのが、僕と同じように年を取った朱音なら何も気にせず答えられたかもしれない。数年ぶりに再会した朱音だったなら、笑ってあの日を過去形にして話せたかもしれない。
でも、今隣にいるのはあの時の朱音なのだ。だから、それではいけない気がした。彼女にとってはまだ「今」なのだ。大人ぶった僕が、嫌な大人みたいに思い出を語ってしまえば、彼女を傷付けてしまう。
いや、それさえ建前なのかもしれない。僕は安心したかったのだ。あの時のあの選択は間違いではなかったと思いたいだけだ。あの瞬間を肯定したいのだ。結局僕は、自分の事しか考えていない。まだ、終わらせたくないから。
「……ごめん、十年前の事だからさすがに忘れちゃった」
大人とはそういうものなのだ、とでも言いたげに嘘をつく。朱音は対して興味も無さそうに「ふーん」と呟く。大人になる度、言葉にできない何かが少しずつ摩耗していく。嘘をつく事への罪悪感もきっとそうだ。
「それで、どう?」
朱音が突然訊ねる。僕は「え?」と間抜けな声を零した。
「何か、十年前に戻れそうな手掛かりになった?」
「……まあ、それだけじゃさすがに難しいかな」
「だよね」
彼女はそう言って、所在なさげな視線を窓の外に移した。彼女の目に、今日の空はどう映っているだろう。十年前の夏のような青空と、今日という日の夏の青空。違いはあるのだろうか。僕にはもう思い出せないけど。
それからまたほんの少し沈黙が場を支配して、僕は何となく考えたことを口にしてみた。
「とりあえず、学校周ってみない?」
「え? なんで?」
「それこそ手掛かりがあるかもしれないし、何か思い出すかも」
席を立ちあがり、教室の出入り口に向かう。特に考えは無かったけど、朱音は納得してくれたようで「まあ、ここにいても仕方ないしね」と僕に付いてきてくれた。
少し埃っぽい廊下を、二人並んで歩く。まるであの日々をなぞっているようだと、あの日々の延長線のようだと、あまりに身勝手な事を思う。それに自己嫌悪もする。
「震は今何してるの? 仕事とか」
「別に、普通の会社員だよ」
「それだけ?」
「それだけって、それ以外に何て言えばいいか」
「ふーん。じゃあ私、は……」
そこで朱音は一度言葉を止めた。僕は聞き返さなかった。
「……いや、やっぱりいい。聴いていいのか分からない」
「……そうだね。聴かないでいいかも」
少し安堵した自分にまた嫌気が刺した。そのまま質問をされていたら、僕は上手く答えられなかっただろうから。
「こうやって学校歩いてると、やっぱり懐かしいって思うの?」
「うん、まあ」
「煮え切らない返事。なに?」
「いや、僕が懐かしいって思うのは学校そのものじゃなくて、君と一緒にいた時間だから」
「……そっか。そうだよね」
彼女が隣で呟く。僕の間違いでなければ、少し悲しそうに。
「私にとってはついさっきの事なのに、君にとってはもう思い出になるんだよね」
しまったと、率直に思った。ついさっき自分に戒めたのに。僕と彼女では、どうにもならない時間の壁があるのに。簡単に過去形を使ってはいけないのだ。
「どうだろう。僕もまだ──」
「……まだ、何?」
「……いや、何でもない」
でも、それを上手く伝えられない。いや、伝える必要はないけれど。でも、僕の今の想いを、感情を、言葉を。彼女に伝えてはいけないのだ。それはただの自己満足でしかないのだから。
しばらく歩いていると、彼女が足を止めて窓の外を見上げた。彼女に近付きながら「どうしたの?」と訊ねてみる。窓の外では、二匹の夏鳥が青空の下でゆっくりと弧を描いている。
「……私がどうなってるのかって君の口から聴けないのは、怖いからなんだ。私はどこにいるのか、何をしてるのか。今の私が感じてるこの焦燥感から抜け出して、私はちゃんと外に飛び出せているのか」
朱音は窓の外から視線を移し、僕の顔を見上げた。僕らのその距離は、十年前よりほんの少しだけ遠くなっている。
「覚えてるかな? ここで君と話した日の事──」
* * * * *
「八月九日。今日の天気は曇り。窓からなんとなく曇り空を眺めてます。気温は高くないのに湿度は高くてイライラします。あ、鳥が飛んでる。なんかイライラします。えっと、あとあれです。今日も何も無い一日でした」
「うおあ」と声にもならない呻き声を漏らし、ポケットにボイスレコーダーをしまう。襟元をばたつかせ、手で自分の首元を仰ぐ。そんな朱音の様子を見ていたら、空を飛んでいた鳥はいつの間にかいなくなっていた。
「何を鳥にイラついてんの」
「だって、鳥ってなんかムカつくじゃん」
「どこが」
「空飛んでるところとか」
「は?」
視線をまた朱音に戻す。朱音の首筋には、うっすらと汗が浮かんでいた。
「私は、どこか遠くに行きたい。ここじゃないうんと遠くに。分厚い雲の切れ目でもいい。青く澄んだ夏空の向こうでもいい。訳も分からないような柵も焦燥も全部取っ払って、早く自由になりたい。鳥みたいに、空を飛んでみたい」
この気持ちはなんだと、誰かに強く問いかけたくなる瞬間がある。今自分が立っている場所が、言いようも無くむず痒くなる瞬間。自分の居場所はここではないと思いたいだけの瞬間。本当に向かうべき場所が、運命のような場所が世界のどこかにあるんだと信じて疑わない瞬間。
「……その気持ちは、よく分かる。多分、僕もそうだから」
でも結局、そんなものは大人に言わせれば思春期という一言で片付けられてしまうものなのだ。この気持ちを手放す事が成長と言うなら、この痛みすら捨て去る事が大人と言うなら、僕はこのままでいい。あの青空の向こう側を、僕は知りたい。
「君は、いつも何か面白い事を探してる。『何も無い一日』に飽き飽きしてる」
ふと思った事を口に出してみる。特に意味は無い。朱音は「なに、急に」と眉を寄せて訝しんだ。
「鳥になって空を飛べたら面白いのかな」
「……どういう意味?」
またどこからか二羽の鳥がやってきて、空の下で弧を描いて飛び回る。
「僕は鳥を見る度、少し悲しくなるんだ。僕らがこの小さな世界から抜け出したいように、鳥もどこにも行けないまま、存在しない出口を探し続けてるんじゃないかって。僕らが世界中のどこに行けるようになったところで、この気持ちは変わらないだろうなって思う。だって、僕はどこまで行っても僕だから。自分以外の、誰かになりたい」
青空の向こう側なんて本当にあるんだろうか。無くたってそれを求めながら死んでいくのではないか。それは虚しくないだろうか。何も変わらないまま、何も変わらない景色を呆然と眺めるだけの存在なんじゃないか。それはやっぱり、悲劇のように思える。
「……でも私は、やっぱり鳥になりたい」
ぽつりと、言葉が口から零れた事に自分でも気が付かないくらいに小さく、朱音が呟く。
「どうして?」
「だって、君は絶対君のままだもん。どこに行こうと、何になろうと。君はどうしようもなく変われないまま」
朱音は、何も無い空を眺めながら言った。飛び回る鳥を目で追いかけながら。あるいは、羨ましそうに見つめながら。
「だから、私は鳥になりたい。大空を飛べるようになれば、また君を見付けられる。君がこの世界にいる限り、君を探し出す。これだけは忘れないで」
どこにも行けない、何にもなれない、何も変われない。それでいい。それがいい。そうやってありもしないものを探す、そんなゴミのような時間でいい。たったそれだけのものを、僕ら二人で大切にしたい。
きっとなんだっていいのだ。まだ名前の無い感情に名を付けるとか、世界で一番綺麗なものを探しに行くとか。ただそこに、お互いがいる事だけが絶対だ。なら、空の向こうを見上げなくとも、変わらずにいる真下の君を見つけに行こう。その為だけに、悲劇と呼ばれようとも翼を広げよう。
朱音は僕に向かって言った後で廊下を歩き出した。僕もそれに付いて行く。
「君って何かと『これだけは忘れないで』って言う癖があるよね」
何だか気恥ずかしくなって、ごまかすように言った。朱音は「そう? 自分じゃ気付かない」と首を傾げる。
「そのせいで僕は覚えてなきゃいけない事が増えるわけだけど」
「忘れられるのは悲しいから。せめて、君には覚えてて欲しいんだ」
「日記みたいにボイスレコーダーで録音してるのも、忘れないように?」
「そうかもしれない」
これも同じだ。きっと理由なんかどうでもいいのだろう。大事なのは、彼女を忘れない事。それだけだ。
「分かった。じゃあ、僕は全部忘れない。ちゃんと覚えておくよ」
僕が言うと、朱音はこちらを振り向いて微笑んだ。そんな綺麗な微笑みを向けられて、忘れられるわけがない。
「約束だからね」
* * * * * *
「約束しただろ、忘れないって。全部覚えてるよ」
窓の外から、白い光が刺している。朱音の驚く表情を鮮明に照らしている。
「君にとってはつい最近の事が、僕にとっては十年前の出来事だけど。それでも、覚えてる。君が忘れて欲しくなかった事も、ボイスレコーダーに録音した事も。何も忘れたくなかったから」
何も忘れたくなかった。何も置き去りにしたくなかった。何もかもを、大切に抱き留めていたかった。彼女と過ごした一瞬一瞬さえあれば、他に何もいらないから。
少し気まずくなって、朱音から目を逸らす。でも彼女は僕の目を真っ直ぐに見つめ、「じゃあ」と思い立ったように言った。
「君がその約束を忘れてないか、テストしよう」
「なにそれ」
僕が訊ねると、朱音は窓の外を指差して口を開く。
「これから学校を周って、そこで私達が何をしたか、何を話したか、何を録音したか。君に全部話してもらう。それを私が答え合わせする」
「ほら、行くよ」と僕の手を取り、そのまま引っ張って行く。ああ、そうだ。こうやって彼女に手を取られる日々の事を、僕は救いと呼んでいたはずだった。
「別にいいけど、そんな事して何になるの?」
少し戸惑いながら訊ねる。彼女は前を向いたまま、「言ったでしょ」と当たり前のようにこう言った。
「世の中の全てに理由とか意味があると思ったら大間違いだって」
彼女は、「私はどうなってる?」と訊きたかったのだと思う。あるいは、「私と君はどうなってる?」と。僕がそれに対して「聴かないでいいかも」と言ったのは、彼女の質問に答えられる自信が無かったからだ。だって、今の僕はもう、彼女と一緒にはいない。どこに行こうと何になろうと、 僕を見つけ出す。そう言ってくれた彼女はいない。
「その時ちょうど雨が降った。それで君が、レコーダーを濡らさないように必死だった」
「傘忘れちゃってさ。君から傘ぶんどったよね」
「君は僕が風邪をひく事よりレコーダーを優先したんだよ」
十年前の彼女と同じように、僕は今、鳥になりたかった。どれだけの時間をかけても、きっと世界のどこかにいる彼女を見つけ出したかった。なのに、僕はどこにも行けないまま、何者にもなれないまま。翼なんか無い。ただ、どうしようもないような現実が目の前にあるだけ。変わらないものなんて無いという、そんな当たり前が、僕を酷く苦しめる。
「年が明けて初めて蝉の鳴き声をここで聞いた」
「私は夏が楽しみだったのに、君は浮かない顔してたね」
「だって、夏なんて馬鹿みたいに暑いだけじゃん」
「それがいいのに」
もう消える事のない何かを抱きしめたまま、あの頃のままの彼女と、あの時の答え合わせをする。こんな事に、意味も理由も無いのに。あの頃の僕は、意味も理由も無い時間を愛おしく思えたのに。
「君に雪玉を投げられた。痛かった」
「覚えてる。その時の震の人を殺しそうな目が面白くてさ」
「笑い事じゃないだろ」
楽しそうな彼女を見る度、僕はただ苦しくなった。僕と彼女がどんな風になろうと、もう僕と彼女の道は交わらないのに。この瞬間がこの先、彼女をどれだけ苦しめるだろう。そう思う。
「震」
「……なに?」
「楽しいね」
……いや、違う。僕は彼女に苦しんで欲しかった。今も苦しんでいると思いたかった。僕だけが、後悔にすらなり切れない感情を抱いているなんて、許せなかった。何も終わらせられないのが僕だけだなんて、思いたくなかった。
「結局私はイルミネーションなんて好きじゃないんだよ」
「どうして」
「だって、寂しくならない。冬は寂しくなる為の季節なのに」
思い出す度に泣きたくなるような朱音が、目の前にいる。この場所に閉じ込められたいと願った。それ以外は何もいらなかった。
「ここで『あと一か月で卒業だね』って君が言った」
「あれ、そうだっけ」
「僕が覚えてるのに君が忘れてどうすんだよ」
「冗談じゃん。覚えてるよ」
もうどこにも行かないでくれと言ってしまいたかった。なのに今この瞬間も、僕と同じように年を取った朱音がどこかにいるかもしれない。僕を探しているかもしれない。僕を待っているかしれない。ありえないけど、一度そう思ってしまうと焦ってしまう。
「それで結局、卒業式の後も教室にいたんだよね」
「僕も君も、他に居場所がなかったからだ」
「笑える」
過去形なんかじゃなかった。終わらせられなかった。何も思い出になんかできなかった。彼女の姿も、歩き方も、指先も、瞳も、流れる髪も、靴先も、その声も。何も忘れたくなかった。ただひたすらに、切実に、彼女の事が。
「十年前に戻る手がかりを探す、なんて、ただの口実だって分かってるんだ。私はただ、君と一緒にいたい。それだけなのにね」
朱音が少し悲しそうに笑う。ふと気付けば、僕らはまた同じ教室に戻ろうとしている。
「……あ」
教室の扉に手をかけた時、僕は一つ思い出したことがあった。
「なに?」
「いや、ちょっと思い出した事があって」
* * * * *
白いブラウスが、熱気を纏って肌にへばりつこうとする。少し苛立ちながら、教室の扉を開ける。
教室には朱音の他に生徒はいない。当然と言えば当然で、今日は夏休み最終日。学校に来ようと思う生徒の方が少ないだろう。それはいい。問題は、扉を開けた瞬間の朱音の様子が、何かを隠すように明らかに挙動不審だった事だ。
「……何してたの?」
「いや、別に」
「……そう」
言いようのない違和感を覚えつつも、自分の席に戻る。それに気を割けないくらい、とにかく暑かったのだ。夏の終わりは、もう少し切ないものだと思っていたのに。
「……なんだよ」
僕を追う朱音の視線があまりにしつこく、思わず訊ねる。けどやっぱり何かを隠しているように「いや、別に」とはぐらかされた。
「今日は録音しないの?」
暑さと視線をごまかしたくて、適当な事を言ってみる。朱音は「え? あ、そうだった忘れてた」と慌てたようにレコーダーを取り出した。
「八月三十一日、今日の天気は晴れ。えっと、何も無い一日でした」
それだけ録音し、レコーダーをポケットにしまおうとする。僕は「え?」と素っ頓狂な声を漏らしていた。
「それだけ?」
「別にいいじゃん」
「せっかく夏の終わりなんだから、もっとなんかあるんじゃないのかなって」
「別に、何も無かったんだから何も無いでいいの」
心に決めたように言い切る朱音を前に、僕は「あっそ」と言うしかなかった。
八月三十一日。夏の終わりを定義するなら、一つの目安にはなるかもしれない。毎年夏は決まったようにやってきて、こうやっていつも通りに終わっていく。何もしないまま終わっていく。これでいいのだろうかと頭の隅で思いつつも、結局何も無いまま。そうやっていくつもの夏を無駄にしてきたような気がする。
「震はさ、今年世界が終わるかも、みたいな話知ってる?」
朱音が思い立ったように言う。僕は「あー」とどこかで聞いた話を思い出した。
「なんとなく。〝2012 〟って映画もあるよね」
「震はあれ信じる?」
「信じるっていうか、信じたいっていうか、本当に終わるといいなって思う」
「どうして?」
僕は少し考え、自分の中にあるその理由を丁寧に崩して言葉にしてみた。一言で表すなら、「安心」という言葉に繋がるかもしれない。
「理由は沢山あるけど、なんか、色々と楽になりそうだからかな」
人間である限り、名前の無い何かに追われる。何かに縋る。何かに葛藤する。何かに苦しめられる。でも、明日世界が終わるとしたら、それも全て無くなるかもしれない。最後の一日だけは、本当に自由になれるかもしれない。その感覚は、少し気になる。
頭の中でそういう風に整理しつつ、「朱音は?」と訊ねてみる。彼女も僕と同じように少し考えるような表情を見せた。
「私は、世界の終わりってどんな光景なのか知りたい。綺麗な景色だといいなって思う」
「分かる。隕石とか降ってきて欲しい」
僕が言うと朱音は「それは風情が無い」ときっぱり言った。風情ってなんだろう。世界の終わりにそんなものがあるだろうか。
「……世界が終われば、私も変われるかな」
「……どういう意味?」
言いたい事は分かるけど、意図が分からずに訊いていた。朱音は何も答えず、ポケットからもう一度レコーダーを取り出す。
「八月三十一日、今日の天気は晴れ。夏の終わりの空はとても綺麗です。世界の終わりもこんな風だといいなって思います。夏の終わりは世界の終わり、なんて、とても甘美な言葉です。早くそうなってくれればいいのに。何も無い一日も、飽きるような毎日も、全部全部ぶっ壊れればいいのに。世界の終わり以上に面白い事なんて絶対に無いのに」
レコーダーのスイッチを切って、小さく息を吐く。その後で、「震」と僕の名を呼んだ。夏の青空のように、とても澄んだ声で。
「私達は、私と君だけは、どこの誰よりも世界の終わりを望むような人間で居続けよう。絶対に。これだけは忘れないで」
「……そうだね」
そうだといいね。言いかけた言葉を裏に隠し、それと似通ったものを取り出す。朱音はまた、少し悲しそうな顔で笑うのだった。
* * * * *
「あの時、教室で何してたの?」
隣の椅子に座る朱音に訊ねる。朱音は「あの時って?」と少し首を傾げた。
「八月三十一日。僕が教室に入った時、何か隠してたでしょ?」
僕が言うと、彼女は何かを思い出したのか「いや、別に」と露骨に顔を逸らした。
「もういいんじゃない? 今更」
ふと、軽く口から零れた言葉。でもそれは、彼女からすればとても重い意味を持つものだ。僕らの間には、どうしたって壊せない隔たりがある。
「今更って、君にとってはそうかもしれないけど、私にとっては過去形じゃないんだから」
でも、僕の心はまだあの日々に囚われたままだ。過去にできない、ならない。朱音の存在はこんなにも僕を蝕んでいる。こんなにも強い呪いがある。
「……僕だってまだ、何も」
続きを言いかけた時、僕のポケットから着信音が鳴った。「ごめん、ちょっと電話」と席を立って廊下に出る。画面には友人の名前が表示されていた。
「もしもし」
『おい、お前今何してんの』
少し焦ったような口調で訊ねられる。まさかタイムスリップした同級生に会っていた、とも言えない。「別に何も」とごまかす。
『お前まさか高校に入ったんじゃねえの』
「入ってないけど」
『ほんとか?』
「うん」
『本当だな?』
「だから入ってないって」
少し大きな声で嘘を吐く。友人は『だってLine送ったあと返信ないから』と落ち着かない様子で言った。思い出してみれば、こいつに言われてここに忍び込んだんだった。
「ちょっと昨日の事思い出して訊いてみたかっただけ」
『そうそう、お前飲み過ぎて二日酔いでフラフラ入って行ったんじゃないかとか』
「大丈夫だから。二日酔いも平気」
これは嘘じゃない。いつの間にか頭痛は無くなっていた。
『びっくりしたよほんと、急に一気飲みとかするから。らしくない』
昨晩の会話を思い出す。高校の話をして、それで朱音の事を思い出して。だから酒に逃げた。酒に逃げられるのは大人の特権かもしれない。
「だってあれはお前が」
そこでふと、こいつが言った言葉を思い出した。
『学生時代の恋愛ってこういうもんだよ。どうせこの先の人生もずっと後悔し続けるんだろうな』
「……お前が」
『この後悔が消えたらいいのに、って思いながら』
『あ~、タイムスリップとかできたらな~』
まさかと思った。
関係があるのか。いや、関係ないと思うのが普通だ。でも、言いようのない確信。拭い切れない納得。
『……俺が、何だよ』
「……何でもない。もう切る」
『は?』
その言葉を最後に、友人との通話を切る。
一つ息を吐いて、教室へと戻る。朱音は変わらず自分の席に座っていた。何か会話をするわけでもなく、その隣に腰を掛ける。
訊ねるべきだろうか。どんな言葉をかけようか。そもそも僕は、彼女に元の場所へ戻って欲しいと思っているだろうか。数多の感情が僕の中で渦を巻いている。
そんな僕を見て何か思う事があったのだろうか。朱音は僕に「ねえ」と声をかけた。とても優しい声、言い換えれば、何かを諦めたかのような声音で。
「震ってさ、後悔とかした事ある?」
「僕は別に──」
ないけど。そう言いかけ、言葉を止める。
朱音と過ごした日々は間違いなく、僕にとっての救いだ。今だってそうだ。あの記憶さえあれば、この先も後ろを向きながらでも生きていけると信じている。
でも一つだけ。どうしても引っ掛かる記憶がある。三月九日。卒業式の後。朱音と別れて、教室を出て、でも教室にもう一度戻って。
もしもあの時、朱音が眠っていなかったら。あの時、扉を開けて朱音を起こしていたら。僕は何をしていただろう。何を言いたかっただろう。答えは分かり切っている。でも、時間を巻き戻せたとして、僕はそうするだろうか。
「……いや、分からない。あれが後悔なのかどうかも」
後悔と呼ぶのは簡単だ。でもそれは、あの日々を否定する事にならないだろうか。もしそうなら、やっぱり後悔とは呼びたくはない。あれでよかったのだと、自分に言い聞かせていたい。
「私はね、たった一つだけ後悔してる事があるの」
朱音の言葉を聴いて、少しだけ悲しくなった。彼女ですら、何かを後悔する事があるんだと、勝手な事を思う。
朱音はポケットからレコーダーを取り出し、スイッチを入れる。録音じゃない。再生だ。
「言おうか迷ったんだけど、私──」
『三月九日、今日の天気は晴れ。二度目の録音です。……言えなかった。今日しかなかったのに。今日じゃなきゃ駄目だったのに。私が今までに伝えた事、何を忘れてもいい。だけど、私の事だけは、忘れないで欲しい。私もこの先、君の事だけは何があっても忘れないからって。そういう風に言いたかったのに。私は、震が──』
「あの日、寝てたんじゃなくて泣いてたの」
「……どうして」
それは、本当にたくさんの意味を込めた「どうして」だった。彼女がそれをどういう風に捉えたかは分からない。でも朱音はちゃんと、僕の疑問に応えてくれた。
「この後悔が消えたらいいのにって思った。今すぐに時間が戻ればいいのにって。まさか、逆に時間が進むとは思わなかったけど」
また、諦めたように悲しく笑う。僕は何を言えばいいのか分からなくて、何を言っても間違いな気がして、ただ口を閉ざした。
「ねえ、震が教室に戻ってきたのってどうして? 私が起きてるって知ってたらどうするつもりだったの? それとも、それすらもう、君の中では思い出なの?」
「違う」
強く断言する。思い出なんかにしてやるものか。まだ、僕の中で全部生きてるんだ。
「思い出なんか一つも無い。過去形にした事なんて一つも無い。後悔なんか一つも無い。だって、あの時言えなかった言葉も、今この瞬間になら君に言えるんだから」
「……じゃあ言ってよ」
少し震えた声で朱音が言う。思わず顔を逸らす。分からないけど、彼女の涙だけは見てはいけない気がした。
「……言えない。それを言うのは、言うべきなのは、君だから。君がその後悔を消さない限り、多分君は戻れない」
理由とか理屈とかはどうでもいい。でも多分、タイムスリップと呼ぶべきこの現象は、後悔がトリガーだ。僕も朱音も、どうしてかそれを薄々感づいていた。でも、見て見ぬふりをしていた。だって。
「……別に、消さなくてもいいって思っちゃうんだ。このままここにいてもいいかなって思っちゃうんだ。だって、また君に会えたんだから」
思わず頷きそうになる。振り向きそうになる。声をかけそうになる。
「でも、やっぱり駄目だよね。このままだと私は、十年後に君と一緒に笑えない。変わらず君といられるように、変わらなきゃいけないんだ」
彼女がいる方向から、音がした。カチカチ。レコーダーのスイッチを入れる音。そして多分、僕らの別れの音。
「十年後の七月四日。今日の天気は晴れ。数分前伝えられなかった言葉を、十年越しの君に伝えます。 何も無い一日でよかった。意味も理由も何も無い世界でよかった。私はただ、君と一緒にいられれば、それ以外は何もいらなかった。震、忘れないで。私は、君がずっと好きです。他の何を忘れても、これだけは忘れないで。……またね」
蝉の鳴き声が聞こえる。風が空を切る音がする。教室から、人の気配が無くなったのが分かる。
「……そんなの、僕だって同じなのに。僕だってそうそう思いたいのに」
なぜだか、無性に苛立っていた。何に、と言われても分からない。暑さかもしれない。自分かもしれない。現実かもしれない。世界かもしれない。分からない。とにかく、死にたいくらいに苛立っていた。
力任せに、自分が使っていた席を思い切り蹴飛ばす。大きな音を立てながら倒れる。
その机の中から、一枚の紙切れがひらりと落ちた。ゴミにしては少し大きく、人の手が加えられたように丁寧に折り畳まれている。拾い上げ、広げてみる。
「朱音 十年後、始まりの場所でまた君と会えますように」
——その瞬間に、僕はもう走り出していた。
『七月四日。今日の天気は晴れ。私は今、 何となく屋上にいます。とにかく暑い。屋上なら少しはマシかなと思って——』
扉を乱暴に開けて教室を飛び出す。
『七月十日。今日の天気は雨。珍しく土砂降りの日です。急な雨で傘を忘れました。とことん最悪の一日です──』
陽を返すリノリウムの床を強く蹴る。
『八月九日。今日の天気は曇り。窓からなんとなく曇り空を眺めてます。気温は高くないのに湿度は高くてイライラします。あ、鳥が飛んでる。なんかイライラします——』
長い廊下に鋭い足音が強く響く。
『八月一日、今日の天気は晴れ。夏が始まりました。蝉がうるさく鳴いています。二か月の命に──』
階段を一段飛ばしで駆け上がる。
『八月三十一日、今日の天気は晴れ。夏の終わりの空はとても綺麗です。世界の終わりもこんな風だといいなって思います。夏の終わりは世界の終わり——』
踊り場で転びそうになる。
『十一月三日、今日の天気は雪。そうです、雪が降りました。震に雪玉をぶつけたらマジで 怒ってました──』
不快な汗が顔を伝う。
『十二月二十四日。今日の天気は晴れ。どこもかしこもイルミネーションだらけです。クリスマスなんて——』
息が切れて胸が締め付けられるように痛む。
『二月九日、今日の天気は曇り。卒業式まで一か月を切りました。もう私達が高校生でいられる時間も──』
構わず走り続ける。
『三月九日、今日の天気は晴れ。言わずもがな卒業式の日です。ずっと立ちっぱなしで足腰が痛い。疲れた。震もしんどそうにしてます——』
夏の香りがする。
『三月九日、今日の天気は晴れ。卒業式の後で教室にいたら、いつの間にか学校から人が消えていました。さすがの私でも違和感を——』
君の声を思い出す。
『十年後の七月四日。今日の天気は晴れ。数分前伝えられなかった言葉を、十年越しの君に伝えます——』
屋上へと続く扉を開ける。
『震、忘れないで。私は、君がずっと好きです。他の何を忘れても、これだけは忘れないで。……またね』
ただ、青いとしか言えない空が広がっている。他には何も無い。夏風が優しく吹いている。
少し広く感じる屋上の真ん中に、ぽつりと何かが置かれている。近付いて見ると、少し古い型のボイスレコーダーだった。見間違うはずがない。彼女が使っていたものだ。
録音履歴の一番上に、今日の日付がある。少し震える手で、再生ボタンを押す。
『七月四日。今日の天気は晴れ。今私は、なんとなく屋上にいます。もう廃校になってしまった私の母校です。
ふと、十年前の不思議な出来事を思い出しました。卒業式の後、私は十年後にタイムスリップしたのです。つまり丁度今、どこかに十年前の私がいるかもしれません。あるいはもう十年前に戻った頃でしょうか。もう断片的にしか思い出せません。全てはただの思い出になってしまいました。
あの頃の私は、あまりに愚直で未熟な恋をしていました。何も無い人生に訪れた彼の存在を、今になってふと想います。私と彼の二人なら、この世界のどこへだって飛べるのだと疑っていなかった。どこにいようと、何になろうと、番のように二人でいられると思っていた。例え世界の終わりが来ようと、その最後の瞬間まで共にいられると祈っていた。例え世界が終わるとしてもその瞬間、私はようやく全てを手に入れられると思った。愛の証明とか、心の場所とか、言葉の輪郭とか。そういう、いくら考えてもしょうがないようなものの答えが分かると思った。どうしようもなく救われない世界で、私と彼だけが救われると思った。たかが世界の終わりと言えてしまうくらい、彼と共にいたかった。
意味も理由もいらないと、昔彼に伝えました。私が今、ここに立っている事にもやっぱり意味も理由もありません。ふと、過去形になったあの日々を思い出したから。それくらいの理由でいいのです。
十年前、机の中に私の想いの丈を記した手紙を入れました。あれを彼が読んだのかどうか、私には分かりません。ですが、彼がここにいないという事はそういう事なのでしょう。
十年前に出会った彼は、今もこの世界のどこかで生きている彼は、もう変わってしまった。多分、私も同じです。変わらないものなんて無いという、当たり前の事実があるだけです。
あるいは、少し時間を置いて彼はここにやってくるのでしょうか。それは嫌だなと少し思います。もう彼にはここに来ないで欲しい。十年前の私を見送った後で、悪い夢を見たようだと思いながらここを去って欲しい。もう、全てを終わらせてさよならして欲しい。強く、そう思います。
何も無い人生でも、ただ彼がいればそれだけでよかった。何を忘れても、私の事だけは忘れないで欲しかった。十年後、始まりのこの場所で君と会いたいと願った。全ては過去形になりました。私も君も変わりました。懐かしい思い出になりました。私はもう、彼に会いたいとは思いません。
これが最後です。彼に伝えたい言葉を、 誰にも伝わらない記録としてここに残します。
ねえ、震。君の事を思い出す度、泣きたくなるくらい、悲しくなるくらい、私はただ、君が好きでした。私はもう、君を忘れます。だから君も、私の事だけはどうか』
カチカチ。レコーダーのスイッチを切る音。
僕らの周波数が、すれ違う音。
『どうか、忘れてください』
ヨルシカ - 声