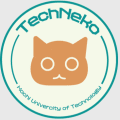今回のテーマは「命の値段」です。
ん~~~、、、何とも難しいテーマですね。
ペット問題を深く考えると必ず最終的に倫理とお金の話になってきます。
テーマ発案者さんが思っていたことは、ざっくり言うと、受け渡し時に大きくお金の動くペットショップシステム、動物福祉的にはおかしな話なんじゃないか、ということだと私は受け取りました。金銭を介してのペットの売り買いは、気持ち良くない、といったところなのかな...?少し解釈違いもあるかもしれませんが。
ですがお金の話は掘り下げると、経済分野の専門性が高くなってくるので、勉強不足の素人が自分なりに解決策なんかを講じると、実現不可能で的外れで一昨日来てくださいな提案になってしまいそうなので、なるべくそこには触れずに、動物の命とお金のつながり方について書いていきたいと思います。
日本ではブリーダーが繁殖させた動物を、ペットショップでお金を介して受け渡しするという流れが基本ですが、ここでの引っ掛かりは、ペット(命)の受け渡しにおいてどうしてもお金が発生してしまう、というのは冷静になって考えると、倫理的でないんじゃない?ということですね。
今の時代は犬も猫もなかなかのお値段で生体販売されています。
もちろんブリーダーが生活していくためには必ず金銭を介し、利益を得る必要があるのですが、動物福祉を考慮したとき、果たして今日本でブリーダーによって行われているペットの大量生産、無暗な品種改良、売れ残ったペットたちの行く末を考えた時、果たしてこのブリーダー中心で、市場の膨れ上がった、利益重視のペット業界の仕組みは正しいと言えるのか、少し考えさせられますね。
ですがここは上述の通り専門性が高いことや、現場を私自身の目で見て確認できていないということがあるので、この記事ではあまり触れないでおきます。
とはいえ、この複雑な問題に考えること、挑戦すること自体は非常に重要なことではあるので、こういった現状、改善の余地があることを皆さんにも知ってもらい、考えていただきたいなと思います。
さて、ここで日本と対照的に動物福祉についての考えが進んでいる動物愛護先進国と呼ばれる国々について紹介したいと思います。動物愛護先進国はヨーロッパに多く、ドイツやイギリス、スイスなどが有名です。
これらの先進国の動物福祉の水準は私たち日本人からすると凄まじいもので、例えばドイツでは、ペットショップでの動物の生体販売自体は法律で禁止されているわけではありませんが、実際店頭に犬猫が並ぶことはほとんどありません。その理由は、ペットショップ業界の自主規制だといいます。一応、動物保護法の規定が厳しく、生体販売を行っても利益があまり見込めないという要因も含まれているとは思いますが、主には社会的に動物福祉の倫理観がしっかり根付いているため、ペットショップが犬猫を販売したら市民からのイメージを損なうというリスクも考慮してのことだと考えられます。
ではそのような状況でペットの欲しい人はどこから探して貰い受けるのかというと、ドイツにはペットショップとは別で、「ティアハイム」と呼ばれる動物保護施設が存在していて、そこでのペットの受け渡しが主流なのです。この施設は行政が民間に委託する形で運営され、主に寄付金で回っています。性質としては日本の動物愛護センターに似ていますが、日本の場合は行政によって税金で運営されているという点、寄付の額がティアハイムに比べて大きく劣るという点などで大きく異なります。
ドイツではこの体制がうまく作用し、犬猫の殺処分数0を長年達成し続けています。
しかしこのティアハイム、ペットショップとは違い、営利団体でないなら、里親となるにはお金が必要ないの?と言われれば、そうではありません。
例えば猫であれば、7000円から18000円ほどの譲渡料が必要です。このお金は運営や飼育のための費用に充てるという意味で集めているものですが、少なくとも猫を譲渡可能な状態にするためにワクチンを接種したり、衛生面のケアをしたり、生まれてから譲渡するまでの餌代だけでも軽くその譲渡料を超えています。つまり、この譲渡料の本当の意味は他にあるということです。
それが、ペットを迎え入れるための「覚悟」として、ということです。
一見すると、命というかけがえのないものをお金で覚悟させちゃうのはどうなのかという引っかかりが起こってしまいそうですが、私はこれは合理的なことだと思います。経済状況は家庭や個人によるとは思いますが、ペットを受け入れるために餌台や生活必需品等の最低限のお金は一生かかりますし、ペットを飼うことによってそれまでの生活も一変することになります。何事もうまく行くわけではないので、ペットを飼ったことでこれまで以上に日常にストレスが増えるかもしれません。
無償であれば、「貰えるし貰おう」的な感覚の人が一定数引き取りにやってくるでしょうが、有償にすることで、その人たちに一度考えて貰える機会になっているんじゃないでしょうか。
それらを鑑みた上で、イニシャルコストを払うことのできない人は、ペットを最期のときまで責任をもって面倒をみることに自信が持てないということなので、ここで1つ、無償であれば不幸な道を辿るはずだったペットの動物福祉が守られましたね。
譲渡料を無償にするということは、最低限のフィルターをも取っ払ってしまうことで、ペットの幸せを考えた時に大きなリスクとなりうるのではないかなと私は考えました。
ん~~~、、、何とも難しいテーマですね。
ペット問題を深く考えると必ず最終的に倫理とお金の話になってきます。
テーマ発案者さんが思っていたことは、ざっくり言うと、受け渡し時に大きくお金の動くペットショップシステム、動物福祉的にはおかしな話なんじゃないか、ということだと私は受け取りました。金銭を介してのペットの売り買いは、気持ち良くない、といったところなのかな...?少し解釈違いもあるかもしれませんが。
ですがお金の話は掘り下げると、経済分野の専門性が高くなってくるので、勉強不足の素人が自分なりに解決策なんかを講じると、実現不可能で的外れで一昨日来てくださいな提案になってしまいそうなので、なるべくそこには触れずに、動物の命とお金のつながり方について書いていきたいと思います。
日本ではブリーダーが繁殖させた動物を、ペットショップでお金を介して受け渡しするという流れが基本ですが、ここでの引っ掛かりは、ペット(命)の受け渡しにおいてどうしてもお金が発生してしまう、というのは冷静になって考えると、倫理的でないんじゃない?ということですね。
今の時代は犬も猫もなかなかのお値段で生体販売されています。
もちろんブリーダーが生活していくためには必ず金銭を介し、利益を得る必要があるのですが、動物福祉を考慮したとき、果たして今日本でブリーダーによって行われているペットの大量生産、無暗な品種改良、売れ残ったペットたちの行く末を考えた時、果たしてこのブリーダー中心で、市場の膨れ上がった、利益重視のペット業界の仕組みは正しいと言えるのか、少し考えさせられますね。
ですがここは上述の通り専門性が高いことや、現場を私自身の目で見て確認できていないということがあるので、この記事ではあまり触れないでおきます。
とはいえ、この複雑な問題に考えること、挑戦すること自体は非常に重要なことではあるので、こういった現状、改善の余地があることを皆さんにも知ってもらい、考えていただきたいなと思います。
さて、ここで日本と対照的に動物福祉についての考えが進んでいる動物愛護先進国と呼ばれる国々について紹介したいと思います。動物愛護先進国はヨーロッパに多く、ドイツやイギリス、スイスなどが有名です。
これらの先進国の動物福祉の水準は私たち日本人からすると凄まじいもので、例えばドイツでは、ペットショップでの動物の生体販売自体は法律で禁止されているわけではありませんが、実際店頭に犬猫が並ぶことはほとんどありません。その理由は、ペットショップ業界の自主規制だといいます。一応、動物保護法の規定が厳しく、生体販売を行っても利益があまり見込めないという要因も含まれているとは思いますが、主には社会的に動物福祉の倫理観がしっかり根付いているため、ペットショップが犬猫を販売したら市民からのイメージを損なうというリスクも考慮してのことだと考えられます。
ではそのような状況でペットの欲しい人はどこから探して貰い受けるのかというと、ドイツにはペットショップとは別で、「ティアハイム」と呼ばれる動物保護施設が存在していて、そこでのペットの受け渡しが主流なのです。この施設は行政が民間に委託する形で運営され、主に寄付金で回っています。性質としては日本の動物愛護センターに似ていますが、日本の場合は行政によって税金で運営されているという点、寄付の額がティアハイムに比べて大きく劣るという点などで大きく異なります。
ドイツではこの体制がうまく作用し、犬猫の殺処分数0を長年達成し続けています。
しかしこのティアハイム、ペットショップとは違い、営利団体でないなら、里親となるにはお金が必要ないの?と言われれば、そうではありません。
例えば猫であれば、7000円から18000円ほどの譲渡料が必要です。このお金は運営や飼育のための費用に充てるという意味で集めているものですが、少なくとも猫を譲渡可能な状態にするためにワクチンを接種したり、衛生面のケアをしたり、生まれてから譲渡するまでの餌代だけでも軽くその譲渡料を超えています。つまり、この譲渡料の本当の意味は他にあるということです。
それが、ペットを迎え入れるための「覚悟」として、ということです。
一見すると、命というかけがえのないものをお金で覚悟させちゃうのはどうなのかという引っかかりが起こってしまいそうですが、私はこれは合理的なことだと思います。経済状況は家庭や個人によるとは思いますが、ペットを受け入れるために餌台や生活必需品等の最低限のお金は一生かかりますし、ペットを飼うことによってそれまでの生活も一変することになります。何事もうまく行くわけではないので、ペットを飼ったことでこれまで以上に日常にストレスが増えるかもしれません。
無償であれば、「貰えるし貰おう」的な感覚の人が一定数引き取りにやってくるでしょうが、有償にすることで、その人たちに一度考えて貰える機会になっているんじゃないでしょうか。
それらを鑑みた上で、イニシャルコストを払うことのできない人は、ペットを最期のときまで責任をもって面倒をみることに自信が持てないということなので、ここで1つ、無償であれば不幸な道を辿るはずだったペットの動物福祉が守られましたね。
譲渡料を無償にするということは、最低限のフィルターをも取っ払ってしまうことで、ペットの幸せを考えた時に大きなリスクとなりうるのではないかなと私は考えました。